

こんにちは。
ファミリーメディカル管理栄養士の鈴木です。
当院には、「咳が止まらない」「だるさが取れない」など、呼吸器に関するお悩みを抱える患者さまが多く来院されます。
私たち管理栄養士は、医師の診察と並行して「分子栄養学」と「選択理論心理学」を掛け合わせた外来カウンセリングを通じ、患者さまの症状改善をサポートしています。
「栄養指導を現場で活かしたい」「患者さまの人生に寄り添いたい」とお考えの方に、当院での仕事のリアルをお伝えします。
1. 喘息に悩む30代女性、咳と冷え性を栄養で改善できた理由

実際に当院の栄養カウンセリングを受けていただいた方のカウンセリング例をご紹介します。
<来院の背景>
Bさん(30代・女性)は、他院で喘息の吸入薬を継続していたものの、夜になると咳が止まらず、慢性的な睡眠不足に悩んでいました。
また「夕方になるとぐったり」「冬場は手足が氷のように冷える」など、強い疲労感と冷え性も併発していました。
初回ヒアリング:生活全体を丁寧に把握
| 質問項目 | 目的 |
|---|---|
| 食事・睡眠・生活リズム | 疲労と生活パターンの相関を探る |
| 食事内容 | 栄養バランスだけでなく好みや調理傾向を確認 |
| 症状メモ | 食事と体調の因果関係を分析 |
| 家族構成・調理担当 | 生活環境と支援者の有無を確認 |
| 食の記憶・好き嫌い | 行動変容の“情緒的価値”を掘り起こす |
Bさんの生活と食習慣
・主食:朝は菓子パン、昼はうどんやパスタ、夜は丼もの中心(小麦中心)
・体調:「お風呂上がりでも手足が冷たい」「夕方は立ちくらみ」
・家庭環境:共働きで、夫が料理担当。協力的。
「パンが大好き」と何度も繰り返されたBさんには、いきなり小麦を制限するのではなく、「お米の頻度を少しずつ増やす」提案をしました。
結果、ご夫婦ともに前向きな反応をいただき、小さな成功体験からのスタートが決まりました。
2. 咳・冷えに共通する“腸内環境”の整え方:3ステップアプローチ

当院の分子栄養学的アプローチは、順番が鍵です。
1.腸内環境の改善
2.タンパク質の補充
3.生活習慣の定着
ステップ1-1|腸内環境の改善:グルテンコントロール
・「パン完全NG」ではなく、全粒粉や米粉パンを提案
・小麦摂取頻度の調整から始める
「パンをやめられない」という不安を払拭するため、Bさんに「無理にやめる必要はありません。パンをやめることに焦点を当てるのではなく、ご飯にする回数を増やすなど、少しずつ変えていきましょう」とお伝えしました。
生活の楽しみを損なわずに、改善の道筋を共有することが重要です。
ステップ1-2|腸内環境の改善:腸内細菌ケア
・乳酸菌生産物質を1日1回摂取
ステップ2|タンパク質のチャージ
・消化機能を見ながら段階的に導入
・「できたこと」に着目し、次の目標は本人が宣言
ステップ3|生活習慣の定着
・患者さまの生活に合わせた「今できることは何か」を一緒に探す
管理栄養士が一方的に課題を出すのではなく、「今週できたことは何でしたか?」「それができた理由は?」と、Bさん自身の言葉を引き出します。
選択理論心理学に基づくこのアプローチにより、Bさんは「やらされている」のではなく「自分で選んでいる」という感覚を持ちながら、主体的に取り組まれました。
3. 継続できた理由と、目に見える変化

食生活を少し見直すだけで、体は確実に応えてくれる——。
そんな前向きな変化を実感できたのが、主食を見直す取り組みを始めたBさんご夫婦です。
「パンはご褒美」「米は日常」と考え方をシフトさせたことで、体調や生活リズムに目に見える変化が現れはじめました。
Bさんが継続できた理由とともに、血液データや日常の体感を通して現れた改善のプロセスを紹介します。
1か月後:夫婦で取り組む主食シフト
「パンはご褒美」「米は日常」にご夫婦での考え方が変化。
Bさんの体感
・寝起きのだるさが軽減
・階段での息切れが減少
・指先の冷えが和らぐ
フィードバック時には、血液データ(中性脂肪・ヘモグロビンなど)と紐づけて成果を可視化し、モチベーションを高めました。
3か月後:咳の頻度が激減
・「ご飯のほうが体に合う」と自ら実感
・咳は1日数回程度に減少
・発作時の吸入薬はほぼ不要に
「前よりも夜にぐっすり眠れるようになった」「気づけば、咳が出ていない日が増えた」と話すBさんの表情は、以前とは見違えるほど明るくなっていました。
これは、単なるデータ上の改善ではなく、生活そのものが好転した証といえます。
ただし、Bさんは「調子が良いとパンを食べすぎそう」と懸念。
そこで月1回の定期カウンセリングで振り返りを行い、リバウンド予防策を提案しました。
4. 成果の裏にある3つの鍵

当院では、患者さまの成果につながるカウンセリングをするために、下記3つの取り組みをしています。
1. 栄養+心理のアプローチ
・「患者さまの価値観」に寄り添い、無理のない提案
・行動変容のハードルを心理面から下げる
2. 症例の多さがスキルを磨く
・週30件以上のカウンセリングで実践経験豊富
・他栄養士との情報交換も活発
3. 毎週の勉強会で知識をアップデート
・院内で、週1回半日業務内で勉強会の実施
多様なケースを日々経験することで、同じ症状であっても異なる背景を持つ患者さまに対して、柔軟に対応する力が養われます。
5. 管理栄養士として感じた、やりがいと喜び

Bさんが3回目の面談で「先生、聞いてください!」と満面の笑みで来られた瞬間、呼吸音も軽く、言葉のテンポも早くなっていて、私は心から感動しました。
「夜ぐっすり眠れるようになり、夫婦でウォーキングも楽しんでいます」
それは、ただの体調改善ではなく、「人生時間」を取り戻したということ。
栄養療法は、患者さまの人生を広げる支援だと確信しました。
6. 管理栄養士として働く魅力

患者さまの変化を感じ、とてもやりがいのある管理栄養士としての仕事。
他にも当院の管理栄養士として働く魅力を紹介します。
チーム医療の一員として深く臨床に関われる
・診療フローに栄養カウンセリングが標準化
・医師や看護師との密な連携あり
教育・研修体制が充実
・栄養カウンセリング実施までに、3か月間の充実した研修制度
・院内動画・資料で分子栄養学を基礎から学べる
週1回の勉強会と情報共有
・外部のセミナー視聴や、大勢のメンバーで行う症例検討など管理栄養士が多数在籍しているからこそできる充実した勉強会
7. 求職者の皆さんへ
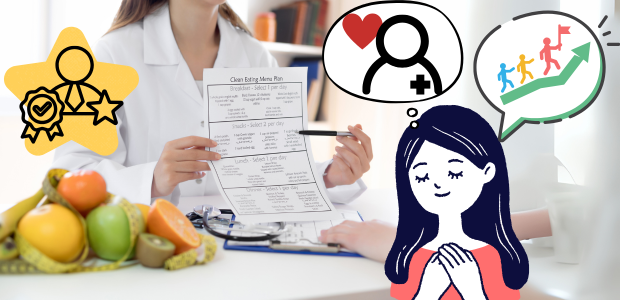
あなたも“外来×栄養療法”のプロフェッショナルに
・病棟給食や集団指導に物足りなさを感じている方
・サプリ・血液データも活用しながら、根本治療を支えたい方
・少人数チームで裁量をもって働きたい方
分子栄養学や心理学の知識は入職後に学べます。
必要なのは「患者さまを良くしたい」という想いと、改善に向けて努力を惜しまない姿勢だけです。
8. まとめ
「患者さまの人生が変わる瞬間に立ち会いたい」
そんなあなたのストーリーを、次は一緒に描いてみませんか?
まずは見学からでも大歓迎。百聞は一見にしかず。
チームの雰囲気や現場の空気感を、ぜひ肌で感じてください。