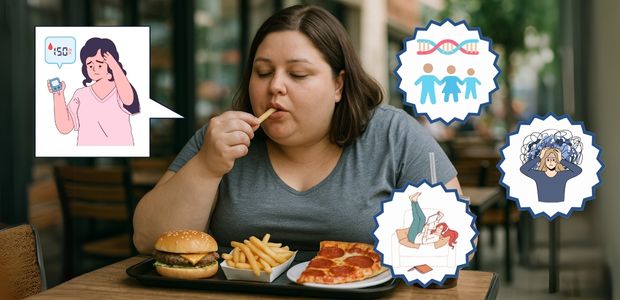糖尿病網膜症とは?気をつけたい目の症状と治療について

糖尿病の合併症のひとつに、「糖尿病網膜症」と呼ばれる目の病気があります。進行すると視力が低下し、最悪の場合は失明してしまうこともあります。
糖尿病を発症してから5~10年ほど経ってから現れることが多い病気なので、まだ先のことと考えてしまいがちですが、自覚症状がないまま進行することが多いため注意が必要です。
この記事では、糖尿病網膜症の症状や治療法、予防のためにできることについて、わかりやすく解説します。
糖尿病と診断されている方は、目の健康を守るためにも、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
目次
1.糖尿病とはどのような病気か
糖尿病とは、血糖値が高い状態が続いてしまう病気です。
<診断基準>
空腹時の血糖値が126mg/dL以上、
または食後2時間後の血糖値が200mg/dL以上
通常、私たちの体では「インスリン」というホルモンが働き、上がりすぎた血糖値を正常な範囲に戻しています。しかし、糖尿病になるとインスリンの分泌量が減ったり、うまく働かなくなったりして、血糖値を下げられなくなります。
糖尿病には、大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは、免疫の異常によって自分のすい臓が攻撃されてしまうことが原因で発症する1型糖尿病。もうひとつは、過食などの不規則な生活習慣や遺伝的な要因によって起こる2型糖尿病です。
糖尿病は、一度かかると根本的な治癒が難しい病気とされています。さらに、発症後は動脈硬化が進みやすくなることで、全身にさまざまな合併症が引き起こされるリスクがあります。
2.糖尿病網膜症とはどのような病気か
糖尿病網膜症とは、糖尿病の合併症として目に現れる病気です。
この章では、糖尿病網膜症の原因や症状について説明します。
2-1.糖尿病網膜症の症状
糖尿病網膜症の主な症状には、以下のようなものがあります。
・視界がぼやける
・一部が見えにくい
・ものが歪んで見える
・黒い点のようなものがちらつく
こうした視覚の異常は両目に同時に現れることもありますが、片方の目から先に発症する場合もあります。
ただし、初期の段階ではこうした症状がほとんど現れないため、異常を感じて病院を受診したときには、すでに病状がかなり進んでいたということも珍しくありません。
異常をそのままにしておくと、症状が悪化して眼内出血や網膜剥離につながり、失明に至る危険もあります。
病気が進行して視力が低下すると、日常生活にもさまざまな支障が出てきます。たとえば、運転免許の更新ができなくなることがあるため、車を使って仕事をしている人や、車が生活の足となっている人にとっては大きな問題となります。
【参考情報】『適性試験の合格基準』警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/other/tekisei03.html
2-2.なぜ糖尿病で目が悪くなるのか
網膜とは、目の最も奥にある薄い膜です。ここには光や色を感じ取る細胞、神経、そして栄養や酸素を届ける毛細血管が集まっています。
網膜にある毛細血管は非常に細く繊細なため、高血糖の影響でダメージを受けやすい場所です。
毛細血管のダメージが蓄積すると、出血や水分の漏れ、血管の詰まりといった問題が起こり、視力に悪影響を及ぼすことがあります。
そのため、糖尿病のある方は目の健康を守るためにも、定期的に眼科で検査を受けることが大切です。
【参考情報】『Retina』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/body/22694-retina-eye
2-3.糖尿病網膜症になりやすい人
糖尿病網膜症になりやすい人には、いくつかの特徴があります。
1.糖尿病の罹患期間が長い人
糖尿病網膜症は、糖尿病と診断されてから5〜10年ほど経過した頃に発症しやすくなります。そのため、糖尿病の期間が長くなるほど、発症リスクも高まります。
2.血糖コントロールがうまくいっていない人
血糖値が高い状態が続いていたり、血糖値の日内変動が大きい場合は、網膜の毛細血管への負担が大きくなります。
3.高血圧、脂質異常症を併発している人
高血圧により血管に強い負担がかかっている人や、脂質異常症で血管内にコレステロールを蓄積している人は、動脈硬化により網膜の毛細血管にもダメージが加わります。
3.糖尿病網膜症の進行段階
糖尿病網膜症は、その進行具合によって3つの段階に分類されます。
それぞれの段階で現れる症状や変化について、くわしく見ていきましょう。
3-1.初期
糖尿病網膜症の初期段階は「単純網膜症」と呼ばれ、網膜にむくみや小さな出血が見られる状態です。
高血糖の影響で血管が弱くなると、「毛細血管瘤(もうさいけっかんりゅう)」という血管のふくらみができやすくなります。これが破れると、小さな点のような出血(点状出血)が起こります。
さらに、血管からタンパク質や脂質が漏れ出して網膜にたまると、「硬性白斑(こうせいはくはん)」と呼ばれる白い沈着物が現れることもあります。
この段階では自覚症状がほとんどないため、自分では気づきにくいかもしれません。
3-2.中期
糖尿病網膜症の中期は「増殖前網膜症」と呼ばれ、初期よりも網膜の血流障害が進行した状態です。血管の閉塞が進むことで、網膜は酸素や栄養が不足し、虚血状態(血流不足)になります。
この状態が続くと、網膜は酸素や栄養を補おうとして、新生血管という異常な血管を作り始めます。
また、網膜の中心部である黄斑(おうはん)部に、血管から液体が漏れ出すことで網膜がむくみ、黄斑浮腫と呼ばれる状態が生じることもあります。
黄斑部は視力にとって非常に重要な部分なので、浮腫が起こると視力が低下します。見え方としては、「視界の中心がぼやける」「ものが歪んで見える」「細かい文字が読みづらい」といった症状が現れることがあります。
【参考情報】『Macula』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/body/23185-macula
3-3.末期
末期の段階は「増殖網膜症」と呼ばれ、新生血管が形成されている状態です。新生血管は、網膜や眼球の約80%を占めている硝子体(しょうしたい)に向かって広がり、出血しやすくなっています。
何度も出血が繰り返されると、硝子体が濁り、急激な視力低下を招くことがあります。さらに、繊維や細胞が集まって「増殖膜」という膜が形成され、この膜が網膜を引っ張ることで、網膜が剥がれて網膜剥離を引き起こすこともあります。
この段階での見え方としては、「突然視界が真っ暗になる」「黒い影が動く」「大きな黒点が見える」「視界の一部が欠ける」といった深刻な視覚障害が現れます。
【参考情報】『Aqueous Humor & Vitreous Humor』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/body/24611-aqueous-humor-vitreous-humor
4.糖尿病網膜症の検査
糖尿病網膜症が疑われる場合は、下記のような検査を実施します。
4-1.眼底検査
目に光を当て、網膜や視神経、血管などの状態を確認する検査です。血管の詰まりや出血、新生血管の形成を直接観察します。
検査の際、瞳孔を広げる散瞳剤が使用されることがあります。散瞳剤を使うと、一時的にまぶしさを感じたり、目のピントが合いにくくなることがあるので、検査当日は車の運転を避ける必要があります。
【参考情報】『眼底検査』日本予防医学協会
https://www.jpm1960.org/jushinsya/exam/exam09.html
4-2.光干渉断層計(OCT)検査
さまざまな角度から、網膜の断面を撮影する検査です。専用の機械に顎を乗せて数秒間目を開け、光を見つめるだけで測定が行えます。
この検査では、糖尿病網膜症による出血や新生血管の有無を立体的に確認できるため、より正確な診断が可能となります。
【参考情報】『OCT(光干渉断層計)検査』KOMPAS|慶應義塾大学病院
https://kompas.hosp.keio.ac.jp/exam/000340/
4-3.蛍光眼底造影検査
網膜の血管の状態をくわしく調べる検査です。造影剤を注入し、眼底カメラで目の血流の様子を撮影します。
この方法で新生血管や出血、血管の詰まりなどの異常を確認し、診断に役立てます。
【参考情報】『蛍光眼底造影検査』KOMPAS|慶應義塾大学病院
https://kompas.hosp.keio.ac.jp/exam/000339/
5.糖尿病網膜症の治療
もし糖尿病網膜症の症状が現れた場合は、できるだけ早く治療を行い、失明を防ぐことが大切です。
5-1.血糖コントロール
最も基本的で重要なのは、血糖コントロールです。血糖値を正常範囲に保つことで、糖尿病網膜症だけでなく、さまざまな合併症の予防にもつながります。
まずは自分の血糖値の経過を確認し、正常範囲内に維持できているかチェックしましょう。もし血糖値が範囲外であれば、食事の見直しや運動、薬物療法を行います。
5-2.レーザー治療
新生血管ができていたり、血管から出血している場合は、レーザー光を使って新生血管を焼き固め、退縮させることで、出血やむくみの進行を防ぎます。また、今後発生する可能性のある新生血管の予防もできます。
治療は外来で行われ、合併症も少ないため、患者さんへの負担は比較的軽いでしょう。治療中はまぶしさや軽い痛みを感じることがありますが、これらは一時的なもので、徐々に軽減していきます。
レーザー治療は、現在の視力を守るための治療です。早期に治療を受けることで、失明を防ぐことができます。
【参考情報】『眼科領域のレーザー治療』日本眼科学会
https://www.nichigan.or.jp/public/disease/treatment/item06.html
5-3.硝子体手術
硝子体出血や網膜剥離などの重度の合併症が発生した場合に行われる外科的治療です。
硝子体とは、眼球内を満たす透明なゼリー状の組織です。この部分が出血で濁ったり、増殖膜に引っ張られたりすると、視力が大きく低下します。
手術は、白目の部分に小さな穴を開け、専用の器具を用いて出血で濁った硝子体を取り除きます。その際、必要に応じて網膜の修復も行われます。
所用時間は1~2時間程度ですが、局所麻酔または全身麻酔を使用するため、原則として入院が必要です。
手術で視力を完全に回復させることは難しいものの、多くの場合、視力が改善します。ただし、視神経に大きな損傷がある場合は、視力回復が難しいことがあります。
【参考情報】『硝子体手術』日本眼科学会
https://www.nichigan.or.jp/public/disease/treatment/item04.html
5-4.抗VEGF治療
VEGF(血管内皮増殖因子)の働きを抑える薬を、目の中に注入する治療法です。治療は短時間で終了し、外来で行うことができます。
糖尿病網膜症では、VEGFが過剰に分泌されることで黄斑浮腫が悪化したり、新生血管が形成されたりすることがあります。
そのため、VEGFの働きを抑えることで、黄斑浮腫の改善や新生血管の形成を防ぎ、視力の回復を促進します。
【参考情報】『抗VEGF治療』日本眼科学会
https://www.nichigan.or.jp/public/disease/treatment/item03.html
6.糖尿病網膜症の予防
糖尿病の合併症には、糖尿網膜症以外にも、神経障害や腎症などがあります。
合併症を防ぐには、食事の見直しや運動、定期的な検診が有効です。
6-1.血糖コントロール
血糖値を安定させるためには、食事、運動、薬物療法を適切に実行することが大切です。糖質を控えつつ、バランスの取れた食事を心掛け、血糖値をコントロールしましょう。
適度な運動を取り入れることでも、血糖値を下げる効果が期待できますが、既に糖尿病網膜症と診断されている人は、運動による血圧変動が網膜の血管に影響を与える恐れがあるので、医師に相談してください。
日々の血糖コントロールは非常に重要です。血糖測定をしている場合は、その結果をしっかり記録しましょう。定期的な健診では、血中ヘモグロビン(HbA1c)を確認し、目標値として7.0%未満を維持することが求められます。
薬で血糖値を調整している場合は、処方された薬をきちんと服用しましょう。薬を正しく福服用しても高血糖が続く場合は、薬の調整が必要なことがあるので、早めに医師に相談しましょう。
6-2.血圧コントロール
血圧が高い状態が続くと、血管に過剰な圧力がかかることで血管の壁が傷つき、動脈硬化が進行します。すると、網膜の血流にも悪影響が及びます。
すでに高血圧と診断されている人は、生活習慣の見直しに加え、必要に応じて降圧薬を使いながら血圧の管理を行いましょう。
6-3.脂質異常症に注意
脂質異常症により悪玉コレステロール(LDL)が血管内に増えると、血管の壁に「プラーク」と呼ばれる塊ができやすくなります。
このプラークが血流を妨げたり、血管の破れやすさを高めたりすることで、網膜の毛細血管の出血リスクが高まります。
脂質異常症を防ぐには、脂質の摂取バランスに気を配りながら、栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。
また、適度な運動を取り入れることで、コレステロールや中性脂肪の代謝が促され、脂質異常の改善にもつながります。
6-4.定期健診
糖尿病と診断された方は、内科の定期健診に加えて、眼科での定期的な検査も年に1~2回欠かさず受けるようにしましょう。
糖尿病網膜症は、初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。
その結果、症状に気付いて病院を受診したときにはすでに視力が低下しており、治療をしても元の視力に戻らないケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐためにも、定期的な目の健診で早期発見することがとても重要です。
7.糖尿病網膜症に関するよくある質問
この章では、糖尿病の患者さんや、糖尿病網膜症の疑いのある患者さんから寄せられるよくある質問と答えを紹介します。
Q1. 糖尿病網膜症になったら、最終的には失明してしまうのですか?
糖尿病網膜症は進行性の病気で完治はしませんが、早期発見と適切な治療を行えば、視力を保つことは十分に可能です。実際、多くの患者さんが定期的な検診と治療によって、視力の低下を最小限に抑えながら日常生活を送っています。
Q2. 眼科での検査は痛いですか?
痛みを伴うことはほとんどありません。ただし、散瞳剤を使う場合はまぶしさを感じたり、一時的にピントが合いづらくなることがあります。
Q3. 糖尿病になると、ほかにも目の病気が起こるのですか?
糖尿病の患者さんは、白内障や緑内障のリスクも高くなります。また、血管の障害により、目を動かす筋肉に信号を送る神経が影響を受けると、眼筋麻痺が起こることがあり、物が二重に見える(複視)症状が出ることもあります。
8.おわりに
糖尿病網膜症は、失明に至ることもある恐ろしい病気ですが、早い段階で治療できれば、視力低下を防ぐことは可能です。「早く気づけば防げる病気」と考えてください。
糖尿病の患者さんは、視力や視野に関する違和感があれば、必ず主治医に相談してください。内科と眼科の連携で、自分では気づきにくい異変をチェックしてもらいましょう。