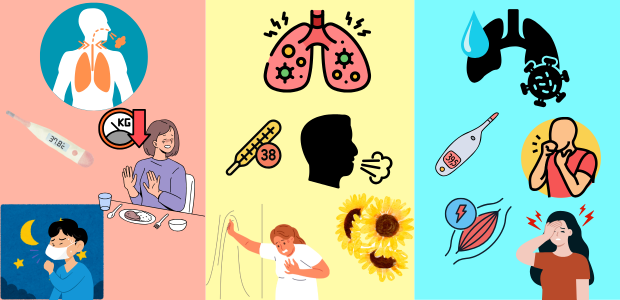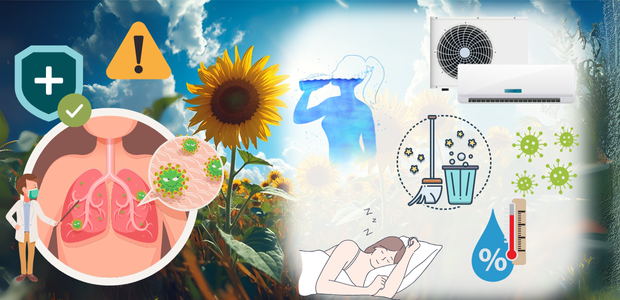夏にも注意!高齢者に多い「夏の肺炎」の症状・原因・予防法を医師が解説

「夏風邪だと思っていたら肺炎だった」という話を聞いたことはありませんか?
実は夏にも肺炎は多く発生しており、特に高齢者では重症化しやすい特徴があります。
夏の肺炎は冬と違って、エアコンのカビや脱水、誤嚥など生活環境の変化が大きく関わっています。
「たかが夏風邪」と油断していると命に関わることもあるため、正しい知識を身につけて予防することが大切です。
目次
1. 夏の肺炎とは何か
夏の肺炎とは、6月から9月頃の暑い季節に発症する肺炎の総称です。
冬の肺炎がインフルエンザウイルスなどの感染症によるものが多いのに対し、夏の肺炎は生活環境や体調の変化が原因となることが特徴的です。
厚生労働省の統計によると、高齢者の肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎であり、夏場は特に脱水や体力低下により嚥下機能が低下しやすくなります。
また、湿度が高い夏場はカビが繁殖しやすく、エアコンの使用開始と共にアレルギー性の肺炎も増加します。
【参考情報】『高齢化に伴い増加する疾患への対応について』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135467.pdf
夏の肺炎が危険な理由は、症状が夏風邪と似ているため発見が遅れやすいことです。
「暑さのせいで体調が悪いだけ」「夏バテかもしれない」と思い込み、適切な治療を受けるタイミングを逃してしまうケースが少なくありません。
特に高齢者は症状が軽微でも急激に悪化することがあるため、早期の対応が重要です。
2. 夏に多い3つの肺炎の種類と症状
夏に発症しやすい肺炎は主に3つのタイプに分けられます。それぞれ原因や症状が異なるため、正しく理解することが早期発見につながります。
2-1. 誤嚥性肺炎
誤嚥(ごえん)性肺炎は、食べ物や飲み物、唾液が誤って気道に入り、そこから細菌感染を起こすことで発症する肺炎です。
夏場は脱水により唾液の分泌が減少し、また暑さによる体力低下で嚥下機能が衰えるため、特に高齢者に多く見られます。
〈誤嚥性肺炎の主な症状〉
・微熱から高熱(37-39℃)
・食後や夜間の咳き込み
・黄色や緑色の痰を伴う咳
・全身のだるさ、息苦しさ
・意識がぼんやりする(特に高齢者)
・食欲不振、体重減少
誤嚥性肺炎の危険信号として、「最近むせやすくなった」「食事の後に咳き込む」「夜中に咳で目が覚める」などの変化があります。
これらの症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
◆『誤嚥性肺炎とは? 食事でむせる・咳き込む人は要注意』について
>>
2-2. 夏型過敏性肺炎
夏型過敏性肺炎は、トリコスポロンというカビを吸い込むことで起こるアレルギー性の肺炎です。
このカビは湿度が高い環境を好むため、梅雨から夏にかけて家の中で繁殖しやすくなります。
エアコンの内部、浴室、洗濯機周辺などが主な発生源となります。
〈夏型過敏性肺炎の主な症状〉
・38℃前後の発熱
・痰のない空咳
・息切れ、動作時の息苦しさ
・全身の倦怠感
・毎年夏に同様の症状が出る
・家を離れると症状が改善する
夏型過敏性肺炎の特徴は、「エアコンを使い始めてから体調が悪くなった」「毎年夏になると風邪のような症状が続く」「旅行先では症状が軽くなる」などです。
これらの症状がある場合は、住環境のカビが原因である可能性を考える必要があります。
◆『夏型過敏性肺炎の症状・原因・治療法|長引く咳の意外な正体』について>>
【参考情報】『過敏性肺炎』日本アレルギー学会
https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/69/5/69_304/_pdf
【参考情報】”Hypersensitivity Pneumonitis Symptoms and Diagnosis” by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/hypersensitivity-pneumonitis/symptoms-diagnosis
2-3. レジオネラ肺炎
レジオネラ肺炎は、温泉施設、ビルの冷却塔、加湿器などの水回り設備に繁殖するレジオネラ菌を吸い込むことで感染する重篤な肺炎です。
国立感染症研究所によると、レジオネラ症は7月を中心に発生件数が増加し、死亡率も高いことが報告されています。
〈レジオネラ肺炎の主な症状〉
・39℃以上の高熱
・頑固な乾いた咳
・激しい呼吸困難
・筋肉痛、関節痛
・下痢、嘔吐、腹痛
・頭痛、意識障害
レジオネラ肺炎は他の肺炎と比べて症状の進行が早く、適切な治療を受けなければ生命に関わる危険があります。
温泉、銭湯、ホテルなどの水回り施設を利用した後に高熱や激しい咳が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。
◆『高齢者の咳には要注意!油断すると危険な理由とは』について>>
【参考情報】『レジオネラ症 2013~2023年』国立感染症研究所
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/533/article/010/index.html
3. 夏の肺炎が見落とされやすい理由
夏の肺炎は冬の肺炎と比べて発見が遅れやすい傾向があります。
3-1. 夏風邪との混同
夏の肺炎の初期症状は、一般的な夏風邪の症状と非常によく似ています。
発熱、咳、だるさなどの症状だけでは区別が困難で、「いつもの夏風邪だろう」と軽視してしまいがちです。
特に高齢者の場合、肺炎でも典型的な症状が現れにくく、「なんとなく元気がない」「食欲がない」「ぼんやりしている」といった漠然とした症状のみが見られることがあります。
このため家族も「暑さで疲れているだけ」と思い込んでしまい、医療機関への受診が遅れることが少なくありません。
夏風邪は、通常2〜3日ほどで症状が軽くなり、水分補給や十分な休養で改善することが多い病気です。
一方で夏の肺炎は、発熱や咳などの症状が1週間以上続き、安静にしても改善しないことが特徴です。
さらに、呼吸のしづらさや息苦しさがある場合は、早めの受診が必要です。
3-2. 症状の軽視
夏場は「暑いから体調が悪くても仕方ない」「夏バテだろう」と症状を軽視する傾向があります。
また、夏休みやお盆などで医療機関の受診を先延ばしにしてしまうことも、診断の遅れにつながります。
さらに、エアコンの効いた室内と暑い屋外の温度差により、体調不良が起こりやすい季節であることも、肺炎の症状を見逃す原因の一つです。
「冷房病かもしれない」と思い込んでしまい、重要な症状を見落としてしまうのです。
4. 夏の肺炎を防ぐためにできること
夏の肺炎は予防可能な病気です。日常生活の中で以下のような対策を取ることで、発症リスクを大幅に減らすことができます。
【参考情報】『ストップ! 肺炎』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/activities/guidelines/file/stop_pneumonia2024.pdf
4-1. 環境の整備
〈エアコン・空調設備の管理〉
・使用前のフィルター清掃と内部の点検
・定期的な専門業者による清掃(年1回以上)
・使用後は送風運転でカビの発生を抑制
・室温は28℃前後、湿度は50-60%に設定
エアコンの内部は結露により湿度が高くなりやすく、カビが繁殖する絶好の環境となります。
夏型過敏性肺炎の主な原因であるトリコスポロンも、エアコン内部で増殖することが多いため、使用前の清掃は非常に重要です。
◆『喘息で気を付けたいエアコンの上手な使い方とは?』について>>
〈住環境の改善〉
・浴室、キッチン、洗濯機周辺のカビ防止
・換気扇の定期的な清掃と稼働
・除湿機の適切な使用
・水回りの水気をこまめに拭き取る
4-2. 体調管理
夏場の体調管理は、誤嚥性肺炎の予防に特に重要です。
脱水状態になると唾液の分泌が減少し、口の中の細菌が増殖しやすくなります。
また、体力が低下すると嚥下機能も衰えるため、以下の点に注意が必要です。
〈水分補給と栄養管理〉
・こまめな水分補給(1日1.5L以上)
・電解質バランスを考慮した水分摂取
・栄養バランスの良い食事
・規則正しい生活リズムの維持
・十分な睡眠時間の確保
特に高齢者は、のどの渇きを感じにくくなっているため、意識的に水分を摂取することが大切です。
スポーツドリンクや経口補水液を活用し、汗で失われるミネラルも同時に補給しましょう。
◆『65歳になったら知っておきたい肺炎の知識と予防』について>>
4-3. 定期的な健康チェック
日本呼吸器学会では、65歳以上の高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの接種を推奨しています。
ワクチン接種により、重篤な肺炎球菌性肺炎のリスクを大幅に減らすことができます。
◆『65歳になったら肺炎球菌ワクチンを受けましょう』について
>>
【参考情報】『成人肺炎診療ガイドライン2024』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/publication/file/adult_pneumonia_2024v5.pdf
肺炎予防には、肺炎球菌ワクチンに加えて、毎年のインフルエンザワクチン接種も有効です。
定期健康診断で胸部レントゲン検査を受け、呼吸器の状態を確認しましょう。
また、日頃から歯磨きやうがいなどの口腔ケアを徹底することも大切です。
さらに、禁煙や受動喫煙を避けることで、肺や気道への負担を減らし、肺炎のリスクを下げることができます。
【参考情報】『肺炎予防のために知っておきたいこと』MSD Connect
https://www.msdconnect.jp/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/pneumovax23-001.pdf
5. こんな症状があったら医療機関を受診
夏の肺炎は早期発見・早期治療が重要です。
以下のような症状が見られた場合は、「夏風邪だろう」と軽視せず、早めに医療機関を受診してください。
5-1. 危険な症状の見分け方
〈すぐに受診が必要な症状〉
・38℃以上の発熱が3日以上続く
・激しい咳や息苦しさ
・黄色や緑色の痰が出る
・胸の痛み
・意識がもうろうとする
・食事や水分が摂れない
・急激な体重減少
特に高齢者の場合は、熱が出なくても注意が必要です。
「いつもよりぼんやりしている」「食欲がない」「会話が少なくなった」などの変化も、肺炎の初期症状の可能性があります。
5-2. 早期受診の重要性
夏の肺炎は適切な治療を受けることで、多くの場合完治可能です。
しかし、診断が遅れると重篤な呼吸不全や敗血症を引き起こし、生命に関わることもあります。
呼吸器内科のある医療機関では、胸部CT、血液検査、痰の培養検査などにより、肺炎の種類を正確に診断することができます。
原因に応じた適切な治療(抗生物質、抗真菌薬、ステロイドなど)を受けることで、症状の改善が期待できます。
◆『呼吸器内科とはどんなところ?何をするのかを解説します』について
>>
診察を受ける際には、症状が出始めた時期やその後の経過を正確に説明しましょう。
また、最近の生活環境の変化(エアコンの使用開始や旅行など)も、原因特定の重要な手がかりになります。
加えて、これまでの病歴や現在服用している薬、家族に同じような症状があるかどうかも医師に伝えることが大切です。
6. 夏の肺炎についてのよくある質問
Q: エアコンを使わない方が良いのでしょうか?
A: 適切に清掃・メンテナンスされたエアコンであれば問題ありません。むしろ適度な除湿により、カビの発生を抑制する効果があります。使用前の清掃と定期的なメンテナンスを心がけてください。
Q: 夏型過敏性肺炎は毎年発症するのでしょうか?
A: 環境中のカビを除去し、湿度管理を適切に行うことで予防できます。一度発症しても、原因となる環境を改善すれば再発を防ぐことは可能です。
Q: 誤嚥性肺炎の予防に効果的な食事の取り方はありますか?
A: 食事の際は姿勢を正し、ゆっくりと咀嚼することが大切です。とろみ剤を使用して飲み込みやすくする、水分補給を十分に行うなどの工夫も効果的です。
Q: レジオネラ肺炎はどこで感染しやすいのでしょうか?
A: 温泉施設、銭湯、ホテルの浴室、ビルの冷却塔、家庭用加湿器などが主な感染源です。これらの施設では適切な水質管理が重要となります。
7.おわりに
夏の肺炎は「見落とされやすい病気」だからこそ、正しい知識と適切な予防対策が重要です。
誤嚥性肺炎、夏型過敏性肺炎、レジオネラ肺炎のそれぞれの特徴を理解し、環境整備と体調管理を心がけることで、多くの場合予防することができます。
特に高齢者やご家族がいる場合は、日頃の体調変化に注意を払い、気になる症状があれば早めに呼吸器内科を受診してください。
「たかが夏風邪」と軽視せず、適切な診断と治療を受けることが、健康な夏を過ごすための第一歩となります。