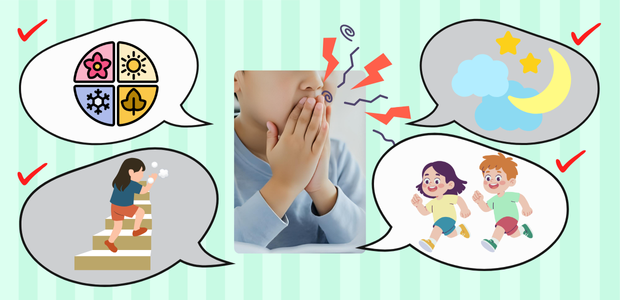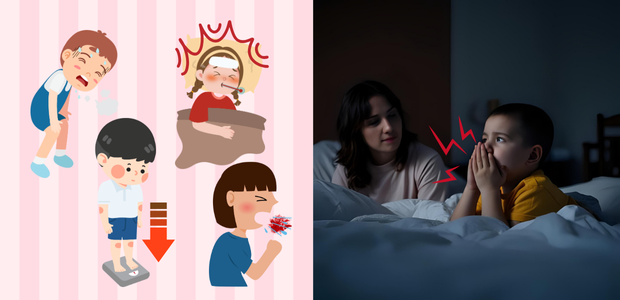子どもの長引く咳は呼吸器内科で相談を!考えられる原因と受診の目安

「子供の咳が長引いていて心配…」「夜中に咳き込んで眠れない様子を見ているのも辛い」そんなお悩みを抱えていらっしゃる保護者の方は多いのではないでしょうか。
お子さんの咳が2週間以上続いているとき、それは単なる風邪ではなく、別の病気が隠れているかもしれません。
この記事では、子どもの長引く咳について、考えられる原因や病院を受診するタイミングなどを分かりやすくお伝えします。
1. 子どもの長引く咳に隠れている病気について
お子さんの咳が長く続いていると、「風邪がなかなか治らないのかな」と思われることが多いのですが、実は風邪以外の病気が原因になっていることがよくあります。
子どもは大人に比べて気道が細く、炎症や刺激の影響を受けやすいという特徴があります。
特に、夜や明け方に咳がひどくなる、運動をすると咳が出る、乾いた咳が何週間も続く、といった症状は、原因をきちんと調べる必要があります。
【参考情報】『急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm
1-1. 風邪の後に残る咳(感染後咳嗽)
風邪の熱や鼻水は治ったのに、咳だけがいつまでも続くことがあります。
これは「感染後咳嗽(かんせんごがいそう)」という状態で、気道が敏感になってしまっているために起こります。
多くの場合は2〜3週間で自然に良くなりますが、1ヶ月以上続くときには別の病気の可能性も考えられますので、一度お医者さんに相談されることをおすすめします。
◆「咳を繰り返す3つのパターンと考えられる病気について」>>
1-2. 小児喘息(しょうにぜんそく)
夜中や明け方に咳がひどくなったり、体育の後に咳が止まらなくなったりする症状は、小児喘息の可能性があります。
喘息は早めに診断を受けて、きちんとした治療を始めることがとても重要です。
特に、ご家族にアレルギーや喘息の方がいらっしゃる場合、ダニやハウスダスト、ペットの毛、花粉などが症状を引き起こしやすいので注意が必要です。
【参考情報】『小児気管支喘息』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-06.pdf
◆「子どもの咳が止まらない…小児喘息の原因と症状、治療法」>>
1-3. マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌によって起こる感染症で、小学生から高校生によく見られます。
「歩く肺炎」とも呼ばれ、熱が下がった後も乾いた咳が数週間続くのが特徴です。
学校や部活動で流行することが多く、咳が2週間以上続く場合は、早めにご相談いただくと安心です。
【参考情報】『マイコプラズマ肺炎』 国立健康危機管理研究機構
https://www.niid.go.jp/niid/ja/mycoplasma-pneumonia-m/mycoplasma-pneumonia-idwrc/2735-idwrc-1239.html
1-4. その他の病気(百日咳、副鼻腔炎、逆流性食道炎)
百日咳(ひゃくにちぜき)は「コンコン…ゼーッ」と連続して咳が出る感染症です。
副鼻腔炎(ふくびくうえん)では鼻水が喉に流れ込んで夜間の咳が増加します。逆流性食道炎では胃酸が逆流して食後や就寝時に咳が強くなります。
これらの病気は「ただの風邪」と区別がつきにくいことが多いので、お医者さんにきちんと診てもらうことが大切です。
【参考情報】『百日咳』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html
【参考情報】『chronic cough』American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/chronic-cough
2. 咳の様子をチェックするポイント
お子さんは自分の症状をうまく説明することが難しいため、お父さんやお母さんが日常生活の中で咳の様子を観察することが、お医者さんの診断にとってとても大きな手がかりになります。
「いつ咳が出るか」「どんな音の咳か」「どれくらい続くか」を意識してメモを取ったり、可能であればスマートフォンで動画や音声を記録しておくと、診察の時にとても役立ちます。
2-1. 咳が出るタイミング
夜中や明け方に咳がひどくなる場合は、喘息の可能性が高くなります。
運動の後に咳が出る場合は、運動で誘発される喘息かもしれません。
食事の後や横になった時に咳が出る場合は、逆流性食道炎が疑われます。
季節の変わり目や台風が近づく時に咳が強くなることもあります。
特定の場所で咳がひどくなる場合は、アレルギーが関係している可能性があります。
2-2. 咳の音や性質
「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音(喘鳴:ぜんめい)が聞こえる場合は、気道が狭くなっているサインです。
乾いた咳なのか、痰が絡んだ湿った咳なのかも重要な情報です。
痰の色や血が混じっていないかも確認してください。
夜中の静かな時間帯は、咳の音がよく聞こえますので、保護者の方の観察がとても重要になります。
2-3. 咳の記録と学校での様子
時間帯、回数、持続時間、一緒に現れる症状を簡単な表に記録する「咳日記」をつけることをおすすめします。
学校での様子も大切な情報です。「給食を残すようになった」「階段を上ると息切れする」といった変化は、病気の早期発見につながります。
3. よくある誤解と注意点
お子さんの咳が長引いていても、「そのうち治るだろう」「熱がないから大丈夫」と考えて、病院に行くタイミングを逃してしまうことがよくあります。
夜中に咳で眠れなかったり、日中の集中力が落ちたりすることは、お子さんの学業や生活の質に大きな影響を与えます。
早めに適切な対応をすることで、これらの問題を防ぐことができます。
3-1. 「咳は自然に治る」という考え方
風邪による一時的な咳の多くは自然に治りますが、3週間以上咳が続いている場合は、「ただの風邪」以外の病気を疑う必要があります。
市販の咳止め薬で様子を見続けていると、重要な病気を見逃す危険性があります。
迷った時は、「念のため」という気持ちで受診していただくのが一番安心です。
3-2. 「熱がなければ心配ない」という考え方
喘息やマイコプラズマ肺炎では熱が出ない、または軽い熱しか出ないことも珍しくありません。
「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音や夜中の咳き込み、食欲不振といった、熱以外のサインを大切にしてください。
3-3. 早期受診の大切さ
咳が長引いても「風邪の後遺症だから」と考えて市販薬だけで様子を見ていると、実際には喘息などの病気が進行し、最終的に入院が必要になるケースがあります。
一方で、2週間程度で早めに受診すれば、咳喘息などの診断を受けて適切な治療を開始でき、学校生活への影響を最小限に抑えることができます。
「早めにお医者さんに診てもらう」ことが、お子さんの日常生活を守る一番の近道です。
【参考情報】『childhood asthma』National Heart, Lung, and Blood Institute
https://www.nhlbi.nih.gov/health/asthma/children
4. 病院での診察と検査について
「子どもが検査を嫌がるのではないか」と心配される保護者の方もいらっしゃいますが、実際の診察はお子さんに負担の少ない方法で進められますので、ご安心ください。
まずは詳しくお話を聞いて、咳のタイミングや原因、これまでの病気などを確認します。
次に、聴診器を使って胸の音を聞いたり、呼吸の様子を観察したりします。
4-1. 主な検査の内容
胸部レントゲン検査で肺炎や気道の状態を確認し、呼吸機能検査で気道の通りやすさを測ります。
血液検査では炎症やアレルギーの原因を調べます。
呼気NO検査は息を吐くだけの簡単な検査で、気道の炎症を調べることができます。
◆「咳が止まらない時に心配な病気の症状・検査・治療の基本情報」>>
4-2. 家庭でできる検査
ピークフロー(息を勢いよく吐き出す力)をご家庭で測定する方法もあります。
小さなお子さんで難しい場合は、症状や診察の結果から総合的に判断します。
検査の前には、お子さんにもわかりやすく説明して、不安を和らげることが大切です。
【参考情報】『Diagnosing Asthma in Children』National Heart, Lung, and Blood Institute
https://www.nhlbi.nih.gov/health/asthma/diagnosis
5. 受診のタイミングと家庭でのケア
お子さんの咳が長引いている時、適切な受診のタイミングを知っておくことで、必要以上に心配することなく、適切な時期に医療機関を受診することができます。
また、ご家庭でできる工夫を取り入れることで、症状の悪化を防ぎ、お子さんが少しでも楽に過ごせるようサポートすることができます。
5-1. 受診が必要なサイン
・すぐに病院に行った方がよい症状:呼吸困難で顔色が悪い、高熱が3日以上続く、血痰が出る、食事が取れない、ぐったりしている
・早めの受診をおすすめする症状:咳が3週間以上続く、夜中に咳で眠れない、「ゼーゼー」音がある、息切れがひどい、食欲不振や体重減少がある
◆「1歳から3歳くらいの子どもが呼吸器内科を受診するめやす」>>
5-2. 家庭でできる具体的なケア
・室内環境の管理: お部屋の湿度は40〜60%に保ち、加湿器は毎日水を取り替え清潔な状態を維持しましょう
・寝具の衛生管理: お布団は週1回以上洗濯し、ダニやアレルゲンを除去してアレルギー症状の悪化を防ぎます
・生活習慣の改善: 生活リズムを整え、バランスの良い食事を心がけて体の免疫力を高めましょう
・水分補給の工夫: 甘い飲み物は控えめにし、温かい飲み物で水分補給をして気道を潤し、咳の症状を和らげます
・症状の記録と準備: 咳日記を続けて症状の変化を記録し、受診時にお医者さんに見せられるよう準備しておきます
5-3. 感染を防ぐための工夫
咳エチケットをきちんと守り、マスクを正しく着けたり、手洗いをこまめに行ったりしましょう。
兄弟姉妹への感染拡大を防ぐため、タオルや食器の共用を避けることも大切です。
学校にも症状について連絡し、集団感染を防ぐためにご協力ください。
【参考情報】『RSウイルス感染症とは』国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/317-rs-intro.html
【参考情報】『RSV in Children』Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/rsv/infants-young-children/index.html
6. おわりに
お子さんの長引く咳は、保護者の方にとって大きな心配事だと思います。
特に3週間以上続く咳や夜間・運動後に悪化する咳は、小児科や呼吸器内科での診察をおすすめします。
早めの診断により、お子さんの症状改善はもちろん、学校生活への影響も最小限に抑えることができます。
ご家庭での環境作りと症状の記録、そして適切なタイミングでの受診を心がけて、お子さんの健康を守っていきましょう。
迷った時は「念のため」の受診が、お子さんとご家族の安心につながります。