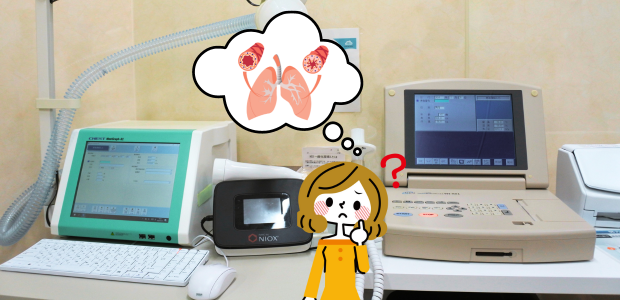呼吸器内科で行われる専門的な検査について

咳が2週間以上続いている場合、喘息なのか、それ以外の病気なのかを正確に判断するために、医療機関ではいくつかの検査を組み合わせて行うことがあります。
呼吸にかかわる喉や気管、気管支、肺などを扱う呼吸器専門クリニックである当院では、必要に応じて以下のような検査を行っています。
・血液検査
・画像検査(レントゲン・胸部CT)
・呼吸機能検査(モストグラフ・スパイロメトリー・FeNO)
・血液ガス分析
それぞれの検査について、簡単に説明します。
◆「その咳、呼吸器内科へ」>>
◆「長引く咳の原因|考えられる病気と受診の目安」>>
目次
1.血液検査
咳や呼吸困難、喘鳴(ぜんめい:ヒューヒュー、ゼーゼーといった呼吸音)といった症状が特徴の喘息はアレルギーが原因で発症することがあるので、血液検査でアレルギーを起こしやすい体質かどうかを調べたり、アレルギーの原因(アレルゲン)となる物質を特定します。
<喘息の原因となるアレルゲンの例>
ダニ、カビ(アルテルナリア、アスペルギルス)、ガ、ゴキブリ、ホコリ、イヌ、ネコ など
<花粉症を引き起こすアレルゲンの例>
スギ、ヒノキ、シラカバ、ブタクサ、ハンノキ(カバノキ科)、イネ科などの花粉
例えば、アレルギーを起こしやすい体質かどうかを調べるためには、IgE抗体というタンパク質の値を測定します。
<総IgE値>
アレルギーのなりやすさを調べます。一般的に200IU/mL以上で高いと判定します。
<抗原特異的IgE抗体>
何がアレルギーの原因(アレルゲン)かを調べます。
【参考情報】『Allergy Blood Test』MedlinePlus
https://medlineplus.gov/lab-tests/allergy-blood-test/
白血球の仲間である好酸球の量も調べます。好酸球はアレルギー性疾患があると増えるので、喘息だと増えることがあります。
アレルギー以外にも血液検査からわかることは多く、感染症が関係していないか、肺炎を起こしていないかなど、さまざまな内容を調べることができます。また自分のアレルゲンを知り、それらを回避することが喘息悪化の予防になります。
2.画像検査(レントゲン・胸部CT)
結核や肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの肺の病気が原因で咳が続くこともあるため、レントゲン検査と胸部CT検査を行います。
◆「結核を疑ったら」>>
◆「肺がんの症状・検査・治療の基礎知識」>>
◆「COPDとは?」について詳しく>>
2-1.レントゲン検査
X線を身体の指定部位にあて、通過した情報から疾患の有無を調べる検査です。
肺炎や結核などの感染症、その他の肺の病気を鑑別するために行います。
2-2.胸部CT検査
体の周囲からX線をあて、通過した情報をコンピューターで解析し、断層写真をつくります。
この検査では、レントゲン検査よりもたくさんの情報を得ることができます。多方向から肺の状況を確認することができるため、肺がんや肺炎などの呼吸器疾患や、胸部の腫瘍などを診断するのに用いられます。
※CT検査は横浜市内の提携病院で実施します。
3.呼吸機能検査
喘息の患者さんは、気道が炎症を起こして狭くなっているため、空気が通りにくくなっています。
呼吸機能検査では、気道がどのくらい狭くなっているのかを調べたり、肺活量などの呼吸機能を調べたりします。
3-1.モストグラフ(MostGraph)
喘息やアレルギー疾患などによって、気管が狭くなっているかどうかを判断する検査です。
マウスピースをくわえ、鼻から空気が抜けるのを防ぐためのクリップをつけた状態で呼吸をすると、呼吸をする時の空気の通り具合が測定できます。
安静な状態で呼吸をすることで測定できますので、患者さんの負担はほとんどありません。
3-2.スパイロメトリー
スパイロメトリーは、肺に出入りする空気、すなわち呼気や吸気の量を測定する肺機能検査のことをいいます。スパイロメーターという機械を使って、呼吸の機能を調べます。
息を大きく吸ったり吐いたり、勢いよく吐き出したりすることによって、肺活量や1秒量などがわかります。思いっきり吸い込んでこれ以上吸えない最大呼気位から、できる限り速く思いっきり吐き出した最大努力呼気で、最後まで吐き切った最大呼気位までが記録されます。
肺活量は、息を最大限吸い込んでから吐き出せる空気の量です。1秒量は、胸いっぱい吸い込んだ空気を、できるだけ勢いよく吐いたうち最初の1秒間に一気に吐くことができる息の量です。
この量が性別、年齢、身長から求めた標準値に比べて少ないときは、気管支が狭くなっている可能性があります。
喘息だと、これらの値が低くなる傾向があります。
3-3.呼気一酸化窒素濃度測定(FeNO)
吐いた息に含まれるNO(一酸化窒素)の濃度を測定する検査です。
喘息やアレルギー疾患で気道に炎症があると、一酸化窒素濃度の値が上がります。喘息の診断や、治療がうまくいっているかなどを判断する材料となります。
喘息の悪化、不安定な喘息や治療不足の喘息の際に一酸化窒素濃度の値が上昇します。また、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などによっても上昇します。ただし喘息発作時には低値を示すこともあるため、適切な診断が重要となります。一般的な目安として、36ppbを超えると喘息が疑われます。
【参考情報】『肺機能検査とはどのような検査法ですか?』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q29.html
4.その他の検査
必要に応じて、以下のような検査も行われます。
4−1.血液ガス分析
血液中の酸素や二酸化炭素の濃度を測定する検査で、動脈から採血して行います。
喘息発作で過呼吸になると、血液中に酸素が取り込まれる一方で、二酸化炭素が多く吐き出されます。動脈血中にあるこれらの量を調べることで、肺が正常に機能しているかどうかがわかります。
◆「喘息発作と間違いやすい「過呼吸」とは?」>>
4-2.気道過敏性テスト
気道に刺激を与える、発作を起こしやすくする薬を使用し、どのくらいの濃度で気道が狭くなるか、発作が起こるかで、気道の過敏の程度を測定します。
※当院では実施しておりません
5.おわりに
咳が2週間以上続いている時は、できれば呼吸器内科のある病院で検査をするのがよいでしょう。
「こんなにたくさんの検査をしないといけないの?」と思われるかもしれませんが、正しい診断のために必要な検査ですから、必ず受けるようにしましょう。
◆「咳が止まらない時に心配な病気の症状・検査・治療の基本情報」>>
検査で気道の空気の流れが悪くなっていることが判明し、その流れが気管支拡張薬で改善される場合は、喘息の可能性が高いです。
喘息の多くは、アレルギー反応とウイルス感染が原因だと考えられています。アレルギーの場合は、原因となる物質(アレルゲン)を避けることが大切です。