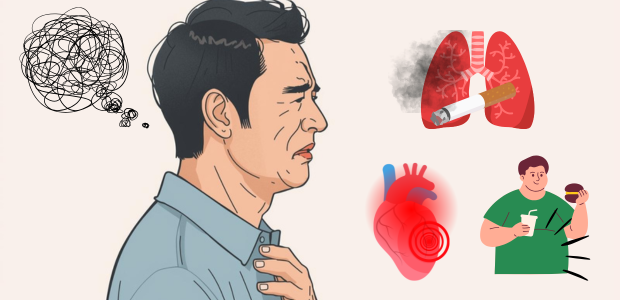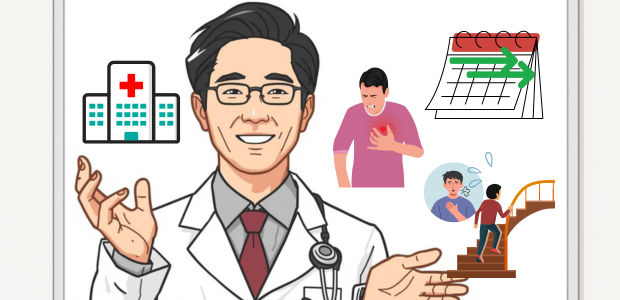息苦しいのは病気?――原因の見分け方と受診の目安

「階段を上っただけで息が切れる」「胸がつまるように苦しくて、思わず深呼吸したくなる」――そんな経験はありませんか。
多くの人は「年齢のせいかな?」「疲れているからだろう」と考えがちです。しかし、息苦しさは体が発している大切なサインであることもあります。
この記事では、息苦しさが起こる仕組みや原因を分かりやすく解説し、医療機関を受診すべきタイミングや、受診までにできるセルフケアについて紹介します。
1.息苦しさとは?
息苦しさとは、「呼吸がつらい」と感じる症状のことです。体内の酸素は足りていても、呼吸に使う筋肉の疲れや心臓・血管の状態、さらには不安や緊張といった気持ちの影響で「息苦しい」と感じることがあります。
つまり、肺や心臓に問題がなくても、ストレスや心配ごとがあると息苦しさが強くなることがあるので、病院で測る酸素の値や検査結果と、本人の自覚が一致しないこともよくあります。
また、日常的に使う「息切れ」という言葉は、運動のあとに息が荒くなるような自然な反応も含みますが、「呼吸困難」という場合は、不快感や苦痛を伴う病気のサインとして使われることが多いです。
2. 息苦しさの主な原因
息苦しさにはさまざまな原因があります。呼吸器の病気に限らず、心臓や血液、さらにはホルモンの異常や生活習慣も関係します。
2-1.喘息
喘息は、空気の通り道である気道に慢性的な炎症が生じて狭くなることで、呼吸がしづらくなる病気です。
夜間や早朝に、咳やゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)という呼吸音が出やすく、発作的に息苦しくなるのが特徴です。
2-2.COPD(慢性閉塞性肺疾患)
長年タバコを吸っていたり、排気ガスや粉じんなどの空気の汚れを浴び続けたりすることで肺が硬くなり、呼吸がしづらくなる病気です。
初めのうちは「年齢のせいかな」と思ってしまいがちですが、運動したときに息切れが出たり、咳や痰が長く続いたりする場合はCOPDの疑いがあります。
◆「咳がとまらない・しつこい痰・息切れは、COPDの危険信号」>>
2-3.肺炎や呼吸器感染症
風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などの呼吸器感染症は、発熱や咳、痰に加え、呼吸困難を伴うことがあります。
特に肺炎は高齢者では重症化しやすく、軽い症状から急に呼吸不全に進行する場合があるため注意が必要です。
2-4.心不全
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなった状態を指します。
主な症状は、息切れやむくみ、体重増加で、横になると苦しいが、体を起こすとラクになる起坐呼吸(きざこきゅう)が見られることがあります。
【参考情報】『心不全で仰向けに眠れず、座っているほうが息が楽になる(起坐呼吸になる)のはなぜですか?』心不全のいろは
https://heart-failure.jp/faq/answer-025/
進行すると安静時にも呼吸困難を感じ、日常生活に大きな制限が生じます。
【参考情報】『Heart failure』Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142
2-5.虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)
心臓を動かすための血管(冠動脈)が細くなったり詰まったりすると、心臓に十分な血液が届かなくなり、胸の痛みや圧迫感が起こります。
この時、息苦しさや冷や汗、左腕や背中に広がる痛みを伴うこともあります。
こうした症状が出たときは、心筋梗塞で命に関わる緊急事態かもしれないので、迷わず119番に連絡してください。
【参考情報】『急性心筋梗塞』国立循環器研究センター
https://www.ncvc.go.jp/coronary2/disease/acute_myocardial/index.html
2-6.貧血
血液の中にある赤血球やヘモグロビンが不足すると、体のすみずみに酸素を届けられなくなり、動悸や疲れやすさ、息切れなどの症状が現れます。
原因の多くは、鉄分不足による鉄欠乏性貧血ですが、長く続く場合は、食事内容や胃腸からの出血など、隠れた原因を調べることが大切です。
2-7.甲状腺疾患
甲状腺ホルモンの働きが乱れると、呼吸にも影響が出ます。
ホルモンが多く出すぎる「甲状腺機能亢進症」では、体の代謝が活発になり、心臓の鼓動や呼吸が速くなるため、息苦しさを感じやすくなります。
一方で、ホルモンが足りなくなる「甲状腺機能低下症」では、筋力や肺の働きが弱まり、少し動いただけでも息切れしやすくなります。
【参考情報】『Thyroid Disease』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8541-thyroid-disease
2-8.肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)
長時間座ったまま動かなかったり、体の水分が足りなくなったりすることで、足の血管にできた血のかたまり(血栓)が肺に流れ込み、肺の血管をふさぐことがあります。
この状態になると、突然、強い息苦しさや胸の痛み、冷や汗、失神などの症状が現れることがあり、命にかかわることもあります。
こうした症状が出た場合は、迷わず救急車を呼んでください。
【参考情報】『エコノミークラス症候群(肺血栓塞栓症)に関するQ&A』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disaster/pcli/
2-9.生活習慣・環境要因
心理的なストレスや過呼吸は、病院の検査では異常が見つからなくても、息苦しさを強く感じさせることがあります。
また、運動不足や喫煙によって呼吸に使う筋肉が弱くなったり、肺の働きが低下したりすると、少し動いただけでも息切れしやすくなります。
さらに、気温の変化や空気の乾燥、花粉やハウスダストなどの環境も、特に持病がある人にとっては息苦しさを悪化させる要因になります。
2-10.肥満
肥満の人が息切れを感じやすいのは、呼吸や循環に関わるいくつもの要因が重なっているためです。
まず、胸やお腹まわりに脂肪がつくと、横隔膜や肺の動きが制限され、1回に吸える空気の量が減ってしまいます。そのため、わずかな動作でも呼吸が苦しく感じやすくなります。
また、体重が増えると全身の組織に必要な酸素の量も増加しますが、呼吸や循環の能力がそれに追いつかないため、酸素不足を自覚しやすくなります。
さらに、体重が増えると体を動かすのがおっくうになり、活動量が減る傾向にありますが、運動不足による体力低下が息切れの要因になることもあります。
3.受診を検討すべきサイン
息苦しさは、疲れやストレスが原因で一時的に起こることもありますが、病気の初期症状である場合もあります。
以下のポイントを参考に、おかしいと思ったら早めに病院を受診しましょう。
3-1.期間と経過
もっとも大切なのは、症状が「続いている時間」と「悪化しているかどうか」です。
<2週間以上続く息苦しさ>
風邪や一時的な体調不良なら、通常は数日で改善します。それが2週間以上続く場合は、何らかの病気が隠れている可能性があります。
<徐々に悪化している場合>
最初は階段を上るときだけ息苦しさを感じていたのに、次第に日常の動作でも息切れするようになった場合は注意が必要です。
3-2.症状の特徴とあわせて出る症状
<夜間や明け方に強まる>
喘息や心不全でよくみられる特徴です。心不全の場合、横になると肺に血液がたまり、心臓への負担が増すために起こります。
<胸の圧迫感や痛みを伴う>
狭心症や心筋梗塞の可能性があります。痛みが左腕や背中、顎に広がる「放散痛」を伴う場合は特に注意が必要です。
<突然の強い息苦しさ・胸痛・冷汗>
肺血栓塞栓症や急性心筋梗塞など、命に関わる病態が疑われます。
<顔色が悪い、めまい、動悸>
貧血や不整脈が関係していることがあります。
<むくみや体重増加>
心不全では体に水分がたまり、下肢のむくみや急な体重増加を伴うことがあります。
【参考情報】『心不全になるとどうしてむくみがでるんですか?』心不全のいろは
https://heart-failure.jp/faq/answer-014/
3-3.緊急時の行動
軽い不安や一時的な息切れなら安静にして様子を見ることもありますが、「今までにない強い苦しさ」「胸の痛みを伴う」「会話ができない」ような状態は救急要請のサイン です。
・急に強い息苦しさが出て、時間がたっても改善しない
・会話が途切れるほど呼吸が苦しい
・胸の痛みや圧迫感、冷や汗、吐き気を伴っている
(心筋梗塞や狭心症の可能性)
・唇や顔が青紫色になる、意識がもうろうとする
(酸素不足のサイン)
・動けないほど苦しい、横になれず座ったまま呼吸をしている
・喘鳴が強く、呼吸をするのが明らかに大変
◆「喘息に多い「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という呼吸音・喘鳴(ぜんめい)とは?」>>
自分で判断できないときは、 #7119(救急安心センター、地域によって対応) などの電話相談を利用するのも有効です。
【参考情報】『救急安心センター事業(♯7119)をもっと詳しく!』総務省消防庁
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate007.html
3-4.受診の目安チェックリスト
救急対応が必要でなくても、次の質問に複数当てはまる場合は、受診を強く検討しましょう。
・息苦しさが 2週間以上続いている
・日常生活での活動が制限されている(階段・会話など)
・夜間や横になると症状が強まる
・胸の圧迫感や痛みを伴う
・急な発症で症状が強い
・めまいや動悸、顔色不良を伴う
・むくみや急な体重増加がある
このチェックリストはあくまでも一般的な目安ですが、当てはまる場合は「ただの疲れ」と考えず、医師に相談することが安心につながります。
4.セルフケアと家族・周囲のサポート
息苦しさが続く場合は受診が第一ですが、軽度で一時的な症状や、受診までの間にできる工夫もあります。
ここでは、自分でできるセルフケアと、家族や周囲がサポートできるポイントを紹介します。
4-1.呼吸法によるセルフケア
不安や過換気に伴う息苦しさを和らげるために有効とされるのが呼吸法です。
<腹式呼吸>
背筋を伸ばして椅子に座り、肩の力を抜いて鼻から息を吸い込みます。お腹が膨らむのを意識しながら、口をすぼめて長く息を吐き出します。これを数分繰り返すことで自律神経が整い、不安による呼吸の乱れが落ち着きやすくなります。
【参考情報】『腹式呼吸のやり方』日本医師会
https://www.med.or.jp/komichi/holiday/sports_02_pop.html
<口すぼめ呼吸>
息を吸った後、ロウソクを吹き消すように口をすぼめてゆっくりと吐き出す方法です。特にCOPD患者の呼吸困難感の軽減に有効とされ、呼吸効率を高めます。
【参考情報】『【実践編】口すぼめ呼吸』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/effective/03.html
4-2.生活習慣の改善
息苦しさを改善するために、日常生活の中で意識できることも少なくありません。
<十分な睡眠と休養>
疲労や睡眠不足は自律神経を乱し、息苦しさを強めます。
<規則正しい食生活>
塩分過多や過度の飲酒は心臓や血圧に負担をかけ、むくみや心不全を悪化させます。
<適度な運動>
医師により許可された範囲での軽いウォーキングやストレッチは、心肺機能を高め、体力低下を防ぎます。
<禁煙>
タバコはCOPDや心疾患の最大のリスク因子であり、禁煙は最も有効な習慣改善策です。
4-3.記録をつける
「いつ」「どんな場面で」「どのくらいの強さで」息苦しさが出るのかを記録することは、診断に大いに役立ちます。
咳や痰の有無、胸痛や動悸、体温や体重の変化などをあわせてメモしておくと、医師が原因を推定しやすくなります。
4-4.家族や周囲のサポート
息苦しさを抱える人を支える上で、家族や周囲の協力も欠かせません。
<症状の観察>
どのようなタイミングで苦しくなるかを一緒に確認し、受診時に医師へ伝える。
<受診の後押し>
「大したことない」と本人が思っても、危険なサインがある場合は受診を勧める。
<環境の整備>
ホコリやカビの除去、空気清浄や加湿による住環境改善。
<緊急時の対応共有>
救急要請の基準や連絡先(119や#7119)を家族全員で確認しておく。
セルフケアはあくまで補助的な手段です。症状が長引く、繰り返す、悪化する場合は「病院に行くのは大げさ」と思わず、医療機関で原因を評価してもらうことが必要です。
5.医療機関でできる検査
息苦しさの原因を特定するためには、医療機関での客観的な検査が欠かせません。
症状や診察所見だけでは判断が難しいため、複数の検査を組み合わせて原因を絞り込むのが一般的です。
5-1.呼吸機能検査(スパイロメトリー)
肺にどれくらい空気を吸ったり吐いたりできるかを調べます。喘息やCOPDがあるかどうか、またその重さを判断するのに役立ちます。
検査では、息を吐く勢いが弱くなっていないか、薬でどのくらい改善するかといった点も確認されます。
5-2.呼気中一酸化窒素(FeNO)測定
喘息が疑われるときに行われる検査のひとつで、気道や気管支に炎症があるかどうかを調べることができます。
5-3.モストグラフ
息をしているときの気道の状態を調べる検査です。特別な動作は必要なく、普段どおり呼吸するだけで、気道の狭さや抵抗の有無を確認できます。
喘息やCOPDなどの診断や経過観察に役立ち、子どもや高齢の方でも受けやすい検査です。
5-4.画像検査
胸部X線検査は、肺炎や心不全、肺の腫瘍など、大まかな異常を見つけるのに役立ちます。
より詳しく調べる必要があるときにはCT検査が行われ、血のかたまり(血栓)や間質性肺炎、まだ小さい段階の腫瘍などを見つけることができます。
5-5.心電図・心エコー
心電図では不整脈や心臓の血流が足りているかどうかを確認でき、心エコーでは心臓がどのくらい力強く動いているかや、弁の働きをその場で見ることができます。
これらの検査は心不全や狭心症・心筋梗塞といった病気の診断につながるため、息苦しさの原因を調べるときにとても重要です。
5-6.血液検査
貧血があるかどうか、体に炎症が起きていないか、甲状腺ホルモンの値が正常かどうかを調べます。
6.息苦しさに関するQ&A
Q1. 息苦しさと動悸はどう違うのですか?
A1. 息苦しさは「呼吸がしづらい」「空気が足りない」と感じる症状で、動悸は「心臓がドキドキと速く打っている」「脈が乱れている」と感じる症状です。両方が同時に起こることもあります。
Q2. 息苦しさがストレスから来ているのか、病気なのかを家庭で見分ける方法はありますか?
A2. 安静にしたり深呼吸で落ち着く場合はストレスや自律神経の乱れの可能性がありますが、明確に見分ける方法はありません。
息苦しさが繰り返す・長引く・悪化する場合は病気の可能性もあるため受診が必要です。
Q3. マスクをすると息苦しくなるのですが、これは病気と関係ありますか?
A3. 多くの場合は正常な反応で、呼吸の抵抗が増えることや心理的な影響で息苦しさを感じやすくなります。
ただし、もともと呼吸器や心臓に持病がある人は、マスク着用で症状が目立つこともあります。
Q4. 息苦しさがあるときに市販薬で対処できますか?
A4. 鼻づまりや軽い風邪が原因なら市販薬で楽になる場合もありますが、心臓や肺、血液の病気が隠れている場合は市販薬では対応できません。
原因が不明の息苦しさには自己判断で薬を使わず、医療機関を受診することが安全です。
7.おわりに
軽度の息苦しさや不安に伴う呼吸の乱れは、腹式呼吸や生活習慣の改善によって和らぐこともあります。
しかし、「2週間以上続く」「日増しに悪化する」「胸痛や冷汗を伴う」「突然強くなった」――こうしたサインは、医師に相談すべきシグナルです。
息苦しさは、誰もが経験する一時的な疲労やストレスによるものから、心臓・肺・血液・内分泌の病気まで、多岐にわたる原因で生じます。
軽度であっても「おかしい」「不安だ」と感じたなら、自己判断で放置せず医療機関を受診することが大切です。
もし、病気が隠れていたとしても、早めに対応すれば治療の選択肢は広がります。