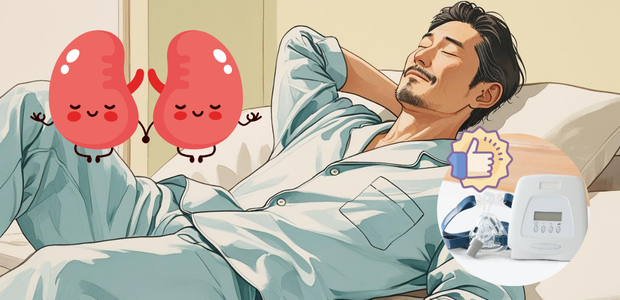睡眠時無呼吸症候群・いびき・腎臓の関係とは?

「いびきをかく」「夜中に何度も目が覚める」「朝から疲れている」——それらは単なる睡眠不足ではなく、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」のサインかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。近年の研究では、この無呼吸状態が全身にさまざまな悪影響を与えることが分かってきました。特に注目されているのが、「腎臓」への影響です。
腎臓病といえば、高血圧や糖尿病が主な原因とされています。しかし、睡眠の質の低下や夜間の酸素不足も、腎臓の機能に影響を与えることが明らかになってきました。
本記事では、睡眠と腎機能の関係性をわかりやすく解説し、合併症の予防や治療継続の大切さをお伝えします。
目次
1.睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、さまざまな生活習慣病を引き起こす危険性がある病気です。
放置すると健康リスクが高まるため、正しい理解と早めの対応が重要です。
1-1.睡眠時無呼吸症候群の特徴と主な症状
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が断続的に止まる、あるいは極端に浅くなる状態が繰り返される病気です。
医学的には、10秒以上の無呼吸・低呼吸が1時間あたり5回以上認められると診断の対象となります。
代表的な症状としては、いびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛、夜間の頻尿、集中力の低下などが挙げられます。
特に肥満、高血圧、糖尿病を持つ方に多くみられますが、やせ型の方にも発症することがあります。
1-2.無呼吸が引き起こす生活習慣病のリスク
睡眠中に無呼吸によって血中の酸素濃度が下がることで、全身の臓器に酸化ストレスがかかります。
また、夜間に交感神経が過剰に働くことで、血圧や心拍数が上昇し、心臓や血管に負担をかけることになります。
その結果、高血圧・不整脈・心不全・脳卒中・2型糖尿病・慢性腎臓病などの生活習慣病を発症するリスクが高まるのです。
2.腎臓の役割と睡眠が腎臓に及ぼす影響
腎臓は、体内の老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出し、血圧や赤血球の生成、骨の健康にも関与する重要な臓器です。
しかし、腎機能が落ちても自覚症状が出にくいため、「沈黙の臓器」とも呼ばれています。
2-1.慢性腎臓病(CKD)とは?
慢性腎臓病(CKD)は、腎機能(eGFR)が60未満の状態が3か月以上続く、または尿タンパクが持続的に出ている状態などを指します。
進行すると透析治療が必要となることもありますが、早期発見と治療で進行を遅らせることが可能です。
【参考情報】『Chronic kidney disease』Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-kidney-disease/symptoms-causes/syc-20354521
2-2.睡眠と腎機能の相互関係
近年の研究では、睡眠の質や睡眠時間が腎機能に影響を及ぼすことが報告されています。
特に、睡眠時無呼吸症候群による低酸素状態が続くと、腎臓の血管に障害を与え、糸球体濾過量(GFR)の低下を引き起こすリスクがあると考えられています。
<睡眠の質と腎機能の関連>
慢性腎疾患患者において、睡眠の質が低下すると腎機能が悪化する可能性があることが示されています。
【参考情報】『Habitual sleep and kidney function in chronic kidney disease: the Chronic Renal Insufficiency Cohort study』National Library of Medicine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28643350/
<睡眠障害と腎機能の関連>
睡眠障害が、慢性腎疾患の進行に悪影響を与える可能性があることが示されています。
【参考情報】『Sleep disorders in chronic kidney disease』Springer Nature
https://www.nature.com/articles/s41581-024-00848-8
<バソプレシンと腎機能の関連>
低酸素や血圧変動は、体内の水分バランスを調整するバソプレシンというホルモンの分泌を増やすことがわかっています。
このホルモンの分泌が増えると、腎臓に負担がかかりやすくなります。
【参考情報】『Vasopressin and Breathing: Review of Evidence for Respiratory Effects of the Antidiuretic Hormone』National Library of Medicine
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8637824/
3.なぜ無呼吸が腎臓に悪影響を与えるのか
睡眠時無呼吸症候群による夜間の酸素不足や血圧の上昇が繰り返されると、腎臓の細い血管に負担がかかり、慢性腎臓病のリスクを高めることがわかってきました。
3-1.酸素不足と腎臓の血管障害
睡眠時無呼吸症候群では、睡眠中に体が酸素不足になることが大きな特徴です。この酸素不足が続くと、腎臓の細い血管にダメージを与えると考えられています。
腎臓は血液がたくさん流れる臓器で、少しの血流の乱れでも機能が落ちやすい構造をしています。
夜間に酸素が減ったり戻ったりする繰り返しが、体にストレスや炎症を引き起こし、腎臓のフィルター部分(糸球体)や尿を作る管(尿細管)に影響を与える可能性があります。
【参考情報】『Kidney』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/body/21824-kidney
3-2.睡眠時無呼吸と夜間高血圧が腎臓に与える影響
睡眠時無呼吸症候群では、呼吸が止まるたびに体が緊張状態になり、夜でもリラックスできずに血圧が下がりにくくなります。
これを「夜間高血圧」と呼び、腎臓に負担をかける原因になります。
さらに、この緊張状態が続くと腎臓につながる血管が細くなり、血流が減ってしまうこともわかっています。
こうした変化が重なることで、腎臓の働きが悪くなり、慢性腎臓病につながるリスクが高まると考えられています。
4.睡眠時無呼吸症候群の治療で腎臓を守る
睡眠時無呼吸症候群の治療で体への負担が軽くなると、腎臓の働きを守ることが期待されます。
4-1.CPAP(シーパップ)療法とは?
CPAP(持続陽圧呼吸療法)は、睡眠中に気道が閉塞しないように空気を送り込むことで無呼吸を防ぐ治療法です。
専用のマスクを装着し、一定の圧力で空気を送り続けることで、気道の閉塞を防ぎます。
CPAPは睡眠時無呼吸症候群治療の第一選択肢とされており、中等度以上の閉塞型の方には保険診療で適用されます。
これにより、無呼吸が改善されることで酸素飽和度の低下や夜間高血圧が軽減し、全身への負担が減ることが報告されています。
4-2.腎機能への影響は?
近年の研究では、CPAPによって、腎機能の低下を抑えたり、腎臓の機能が低下すると増える尿中のアルブミン量が改善する可能性があると報告されています。
【参考情報】『Albuminuria (proteinuria)』National Kidney Foundation
https://www.kidney.org/kidney-topics/albuminuria-proteinuria
とはいえ、「腎臓を直接治す治療」ではなく「腎臓に負担をかけにくい環境を整える治療」と考えることが大切です。
CPAPは腎臓に直接働きかけるわけではありませんが、夜間の酸素不足や血圧上昇、自律神経の乱れといった腎臓に負担をかける要因を減らすことで、結果的に腎臓を守ることにつながると考えられています。
5.自分が当てはまるかチェックしてみましょう
<睡眠時無呼吸症候群チェックリスト>
・いびきをかくことが多い
家族やパートナーに「いびきが大きい」と言われることがある
・夜中に息が止まっていると言われた
寝ている間に呼吸が止まったり、苦しそうにしていると指摘される
・日中に強い眠気を感じる
仕事中や運転中にウトウトしてしまうことがある
・夜中に何度も目が覚める
頻繁にトイレに行く、息苦しさで目が覚めるなど睡眠が途切れる
・集中力や記憶力の低下を感じる
疲れやすい、物忘れが増えた、仕事や勉強に集中しにくい
<腎機能チェックリスト>
・むくみが出やすい
朝起きたときや手足・顔がむくむことがある
・尿の異常を感じる
泡立ちが強い、色が濃い、血が混ざるなどの変化がある
・疲れやすい
日常生活で疲れやすく、回復しにくい
・高血圧がある
血圧が高めで、薬を飲んでいる場合も注意が必要
・体重が急に増えたり減ったりする
むくみや水分の異常が影響していることがある
睡眠時無呼吸症候群は、自分では気づきにくく見過ごされやすい病気です。ですが、自宅でできる簡単な検査で、睡眠中に呼吸が止まっていないかを調べることができます。
また、腎臓の働きも血液検査(eGFRやクレアチニン)や尿検査(尿タンパクやアルブミン)で手軽にチェックできます。
【参考情報】『腎臓の機能をチェックしてみましょう』日本腎臓財団
http://www.jinzouzaidan.or.jp/jinzou/jinzou_4.html
どちらの病気も自覚症状が少ないまま進行することがあるため、早めの検査と定期的なチェックがとても大切です。
6.睡眠時無呼吸症候群と腎臓に関するよくある質問
Q1. 睡眠時無呼吸症候群の治療を始めたら、どのくらいで腎機能への効果が出ますか?
A. 個人差はありますが、CPAP療法などを数か月から1年ほど継続することで、腎機能の低下スピードが緩やかになったり、尿検査の数値が改善するケースが報告されています。
Q2. 腎臓に負担をかけにくくするために、普段の生活でできることはありますか?
A. 体重管理、減塩、適度な運動、十分な水分補給が腎臓を守る基本です。また、アルコールや喫煙は睡眠の質を下げ、腎臓にも悪影響を与えるため控えるのがおすすめです。
Q3. 睡眠時無呼吸症候群と腎臓病を同時に予防するにはどうすればよいですか?
A. 「生活習慣を整えること」が共通の予防策です。肥満防止・減塩・禁煙・飲酒の制限に加えて、睡眠環境を整え、早めに検査を受けることが大切です。早期発見と治療の継続が、両方の病気の進行を防ぐカギになります。
7.おわりに
睡眠時無呼吸症候群と腎機能は、一見関係がないようでいて、血圧・酸素・交感神経といったメカニズムを通じて密接に関係しています。
いびきや日中の眠気を「年齢のせい」と片づけてしまっていませんか? 睡眠の質が下がることは、疲れだけでなく、腎臓を含むさまざまな臓器に影響を及ぼすリスク要因になります。
気になる症状がある方はぜひ一度ご相談ください。早期に気づき、適切に治療することが、これらの病気の進行を防ぐカギとなります。