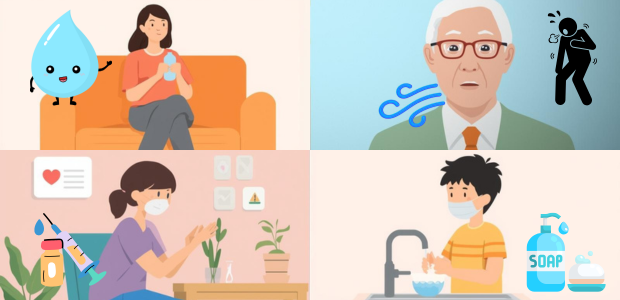インフルエンザの合併症に注意!危険なサインと受診の目安
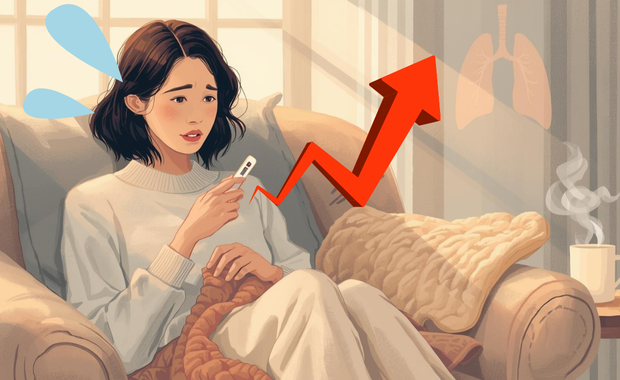
インフルエンザは、発熱・関節痛・倦怠感などの症状を伴い、通常は5〜7日程度で改善するとされています。
しかし、「熱は下がったのに咳が続く」「胸が苦しい」「再び発熱した」といった声は少なくありません。こうした症状が長引く場合、単なる回復途中ではなく「合併症」が起きている可能性があります。
特に、高齢者・小児・基礎疾患を持つ方では、体力や免疫の働きが低下しているため、インフルエンザそのものよりも合併症の方が重くなることがあります。
この記事では、インフルエンザに伴う主な合併症と注意すべき症状、そして「どの診療科を受診すべきか」について分かりやすく解説します。
もし今、インフルエンザ後の体調不良が続いている方は、ご自身やご家族の体を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。
目次
1.インフルエンザの合併症とは
インフルエンザはウイルスが原因で起こる急性呼吸器感染症で、体の免疫が強く反応することで全身に炎症が起こります。
ふつうは数日で回復しますが、ウイルス感染で別の病気が引き起こされることがあります。これを「合併症」と呼びます。
特に高齢者や、喘息・心臓病・糖尿病などの持病がある人は、免疫の働きが一時的に弱くなり、肺や心臓などに影響が出やすくなります。
インフルエンザの後に咳や息苦しさ、再びの発熱が出る場合は、こうした合併症が起きている可能性があります。
これらの合併症は、インフルエンザが直接的に引き起こすものだけでなく、ウイルスによる粘膜のダメージが原因で細菌感染を誘発するケースも多く見られます。
つまり、「治りかけているのに再び症状が強くなった」という場合は、体内で新たな感染や炎症が起きているサインとも考えられるのです。
【参考情報】『Signs and Symptoms of Flu』CDC
https://www.cdc.gov/flu/signs-symptoms/index.html
2.代表的な合併症とその症状
インフルエンザにかかったあと、「熱が下がったのにまだ体がつらい」「咳が止まらない」といった状態が続くときは、合併症の可能性を考える必要があります。
ここでは、代表的な合併症とその特徴的な症状を紹介します。
2-1. 肺炎・気管支炎
最も多い合併症のひとつが肺炎や急性気管支炎です。インフルエンザウイルスで弱った気道に細菌が感染し、肺や気管支に炎症が起こることで発症します。
<主な症状>
・咳や痰が長引く、または増える
・発熱が一度下がってから再び上がる
・息苦しさや胸の痛みがある
・呼吸をすると「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と音がする
特に高齢者では、発熱が目立たず、倦怠感や食欲不振だけで進行することもあります。放置すると重症化して入院が必要になることもあるため、早めの受診が重要です。
2-2. 喘息の悪化
インフルエンザをきっかけに、喘息や咳喘息が悪化するケースもあります。ウイルス感染によって気道の粘膜が敏感になったことが原因です。
<主な症状>
・夜間や早朝に咳き込む
・胸が締めつけられる感じがする
・会話や笑いで咳が出やすい
これらは一時的な風邪ではなく、気道の炎症反応が続いているサインです。
2-3. 心筋炎・脳炎などの重症合併症
頻度は高くありませんが、心筋炎や脳炎・脳症などの全身性合併症が起こることもあります。これらは重症化すると生命に関わるため、早期発見が非常に重要です。
以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
・強い胸の痛み、動悸、息苦しさ
・意識がもうろうとする
・けいれんが起こる
・強い頭痛やふらつき
これらの症状は、病気の後の体力低下とは異なります。「おかしい」と感じたら、迷わず受診することが大切です。
【参考情報】『心筋炎とは』日本心臓財団
https://www.jhf.or.jp/check/opinion/category/c15/
3.どの診療科を受診すべき?迷ったときの目安
インフルエンザの回復期に「咳が続く」「熱がぶり返した」「体がだるい」といった症状がある場合、どの診療科に行くべきか迷う方は多いものです。
体のどこに炎症が起きているかによって、適切な診療科は異なりますが、判断が難しいときは、まず呼吸器内科を受診するのがいいでしょう。
3-1. 咳・息苦しさ・胸の痛みがある場合
インフルエンザ後の肺炎や気管支炎、咳喘息などはすべて呼吸器内科の領域に含まれます。
呼吸器内科では、聴診・レントゲン・血中酸素飽和度測定などによって、肺や気道の炎症の有無を早期に把握できます。
「風邪やインフルエンザの延長」と思って放置しているうちに肺炎が進行していた、というケースも少なくありません。
息苦しさが強いときや、横になると咳き込みがひどくなる場合は、早めの受診が必要です。
3-2. 耳や鼻に痛みや詰まりがある場合
インフルエンザ後に耳の奥が痛む、鼻づまりや頭痛が続く場合は、耳鼻咽喉科の受診が適しています。
このような場合、中耳炎や副鼻腔炎を起こしていることがあり、抗菌薬や鼻処置が必要になることもあります。
ただし、呼吸器症状も同時にある場合は、まず呼吸器内科で全身状態を確認してもらい、必要に応じて耳鼻科を紹介してもらうのが安心です。
3-3. 強い倦怠感・動悸・胸痛がある場合
全身のだるさや胸の痛み、脈の乱れを感じるときは、内科または循環器内科での診察が必要です。
心筋炎や脱水、電解質異常(体内のナトリウムやカリウムなどのミネラルのバランスが崩れた状態)などの可能性もあるため、血液検査や心電図検査を行うことがあります。
【参考情報】『心電図検査ってどんなものですか』日本心臓財団
https://www.jhf.or.jp/check/ecg/inspect/
3-4. 迷ったら呼吸器内科へ
インフルエンザ後の不調は、複数の臓器が関わっていることが多く、自己判断では区別がつきにくいものです。
そのため、「咳・息苦しさ」などの呼吸器症状が中心の場合は、まず呼吸器内科を受診するのが最も適切です。
必要に応じて他科への紹介も行われるため、結果的に最短で正しい診断にたどり着けます。
4.インフルエンザ合併症を防ぐための対策
インフルエンザの合併症は、誰にでも起こる可能性がありますが、日常生活の中で少し意識するだけでもリスクを下げることができます。
ここでは、回復期の過ごし方と予防のためのポイントを紹介します。
4-1. 回復期は「無理をしない」が最も大切
熱が下がると、「もう治った」と思いがちですが、体の中ではまだ炎症や免疫反応が続いています。
体力が完全に戻る前に無理をすると、免疫の働きがさらに低下し、肺炎などの合併症を引き起こすリスクが高まります。体のだるさが残る間は、十分な睡眠と栄養をとりましょう。
また、水分補給は非常に重要です。発熱や呼吸によって体内の水分は想像以上に失われています。こまめに水やお茶、経口補水液を摂取し、脱水を防ぎましょう。
出勤・登校の再開は、解熱後2日以上たってからが目安です。
咳が続く間はマスクを着用し、周囲への感染を防ぐとともに、自身の喉も守りましょう。
4-2. 慢性疾患のある方・高齢者の注意点
高齢者や、糖尿病・心疾患・呼吸器疾患(COPDや喘息など)を持つ方は、インフルエンザをきっかけに持病が悪化することがあります。
症状が軽くても油断せず、次のような点に注意してください。
・吸入薬や定期薬を自己判断で中止しない
・咳や息苦しさが強い場合は早めに主治医または呼吸器内科へ
・体温が上がらなくても、息切れや倦怠感がある場合は肺炎を疑う
4-3. 予防接種と日常の感染対策
毎年のインフルエンザワクチン接種は、重症化や合併症を防ぐ上で非常に有効です。特に高齢者や持病のある方は、流行期の前に接種しておくことで安心です。
また、手洗い・うがい・室内の加湿・バランスのとれた食事といった基本的な生活習慣が、合併症の予防にもつながります。体力と免疫力を保つことが、最も確実な防御策といえるでしょう。
5.受診が必要な危険なサイン
インフルエンザは、多くの場合は自然に回復しますが、「合併症を起こしているサイン」を見逃すと、症状が急速に悪化することがあります。
特に次のような状態がみられた場合は、できるだけ早く医療機関を受診してください。
5-1. 熱が5日以上続く、または一度下がってから再び上がる
通常、インフルエンザの発熱は3〜5日でおさまります。いったん解熱したあとに再び熱が上がる場合は、肺炎や気管支炎などの二次感染を起こしている可能性があります。
再発熱は「回復ではなく悪化のサイン」と捉え、受診をためらわないことが大切です。
5-2. 咳・痰・息苦しさが強い
「咳が長引く」「痰の量が増えた」「息苦しい」などの呼吸器症状は、呼吸器内科での診察が必要です。
特に、「夜間に咳き込む」「横になると息がしづらい」といった症状がある場合は、肺に炎症が広がっている可能性があります。
5-3. 強い倦怠感や胸の痛み、動悸がある
体全体がだるく、胸の痛みや脈の乱れを感じるときは、心筋炎や脱水、電解質異常などの可能性があるので軽視せず、すぐに医療機関で検査を受けてください。
特に「胸の痛みが続く」場合は軽い症状でも、呼吸器や循環器の異常が隠れていることがあります。
5-4. 意識のもうろう、けいれん、ふらつき
脳炎や脳症など、重篤な合併症のサインである可能性があります。これらは時間との勝負です。すぐに救急外来を受診するか、救急車を呼ぶ判断が必要です。
5-5. 高齢者や持病のある方の体力低下
高齢者では、発熱や咳が目立たなくても、食欲の低下や歩行時のふらつき、息切れなどが初期サインとなることがあります。
こうした「危険なサイン」は、本人よりも周囲が先に気づくこともあります。家族が異変を感じたら、早めに受診を勧めましょう。
6.インフルエンザの合併症に関するよくある質問
Q1. 「合併症」と「後遺症」はどう違うのですか?
A1. 合併症は、インフルエンザの経過中に肺炎など別の病気が起きること、後遺症は、治った後に症状が残ること(例:長引く咳や疲労感など)を指します。
Q2. 合併症が起きた場合、市販薬で様子を見ても大丈夫ですか?
A2. 咳止め薬や解熱薬で一時的に症状が軽くなることはありますが、合併症自体が治るわけではありません。再発熱や息苦しさがある場合は、必ず医療機関を受診してください。
Q3. インフルエンザの検査で陰性でも合併症の可能性はありますか?
A3. あります。ウイルス自体がすでに体内から減っていても、肺炎や気道炎などの炎症が進行していることがあります。検査結果よりも「症状の変化」で判断することが重要です。
7.おわりに ― インフルエンザ後も油断せず、早めの受診を
インフルエンザは一見「よくある季節の病気」と思われがちですが、治った後に起こる合併症は決して珍しくありません。
回復期の体は非常にデリケートです。無理をせず、十分な休養と水分補給を心がけ、体調に少しでも異変を感じたら医療機関に相談しましょう。
特に咳・息苦しさ・再発熱があるときは、自己判断せずに呼吸器内科の受診をおすすめします。
呼吸器内科では、胸部レントゲン検査や呼吸機能検査、血液検査などを通じて、肺や気道の炎症の程度を正確に判断することができます。
早めに専門的な診察を受けることで、重症化を防ぎ、安心して日常生活に戻ることができます。