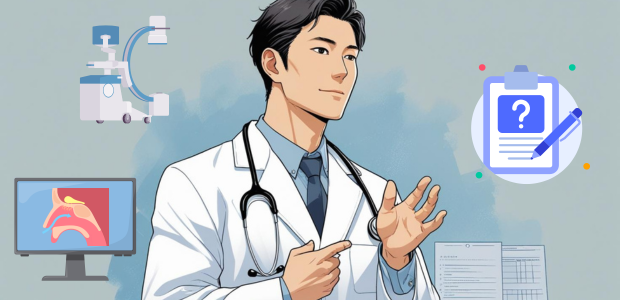副鼻腔炎とはどんな病気?咳・アレルギー・いびきとの関係

私たちの顔の中には、副鼻腔(ふくびくう)と呼ばれる空洞が存在しています。この副鼻腔に炎症が起こる病気が副鼻腔炎です。
副鼻腔は額(前頭洞:ぜんとうどう)、頬(上顎洞:じょうがくどう)、鼻の奥(蝶形骨洞:ちょうけいこつどう)、そして目の間(篩骨洞:しこつどう)にあり、それぞれ鼻とつながっていて、呼吸や声の響きに影響を与えています。
副鼻腔の内部は粘膜に覆われており、鼻と同様に外部からの異物を排除したり、空気の湿度を調整する役割を担っています。
この記事では、副鼻腔炎の症状・治療法・予防法のほか、咳やアレルギー、いびきとの関係について解説します。
目次
1.副鼻腔炎の種類と症状
何らかの原因で副鼻腔の粘膜が腫れると、粘液の排出がうまくいかず、副鼻腔に膿がたまって炎症が起こります。これが副鼻腔炎です。
1-1.副鼻腔炎の種類
副鼻腔炎には「急性」と「慢性」の2種類があります。急性副鼻腔炎は、風邪などをきっかけに一時的に炎症が起こるもので、通常は1〜4週間ほどで自然に改善します。
慢性副鼻腔炎は3か月以上症状が続く状態で、繰り返し再発したり、「鼻茸(ポリープ)」ができたりすることもあります。
【参考情報】『Sinus Infection (Sinusitis)』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis
さらに、慢性副鼻腔炎の中でも特に難治性で再発を繰り返すタイプとして、「好酸球性副鼻腔炎(Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis:ECRS)」があります。
これは、好酸球という炎症に関わる白血球が副鼻腔内に大量に集まることで、強い炎症と鼻茸の形成を引き起こす病態です。
一般的な慢性副鼻腔炎と比べて薬が効きにくく、手術を行っても再発しやすいのが特徴です。喘息を合併することも多く、全身的なアレルギーの関与が疑われています。
1-2.副鼻腔炎の主な症状
副鼻腔炎の症状は主に鼻に現れますが、鼻水の影響で咳が出ることもあります。
<鼻水・鼻づまり>
代表的な症状として、鼻水や鼻づまりが挙げられます。特に粘り気のある黄色や緑色の鼻水が出ることが多く、風邪のときとは異なる濃い色と臭いが特徴です。
鼻の奥に膿がたまっている状態で、鼻をかんでもなかなかスッキリせず、不快感が続きます。
また、鼻がつまることで口呼吸が習慣化し、喉の乾燥やいびき、集中力の低下など、日常生活にさまざまな影響を及ぼします。
◆「口呼吸がいびきにつながる理由と予防のためにできること」>>
<頭痛・顔の痛み>
副鼻腔に膿がたまると、周囲の神経が刺激されて、額や目の奥、頬、鼻の根元などが痛むことがあります。特に前かがみになったときや頭を動かしたときに痛みが増すのが特徴です。
歯の痛みと勘違いされることもあり、歯科を先に受診する方も少なくありません。顔の痛みが長引く場合には、副鼻腔炎の可能性も視野に入れておくことが大切です。
<咳や喉の違和感>
副鼻腔炎では、鼻水が喉の奥に流れ込む「後鼻漏(こうびろう)」がよく見られます。これにより、喉に違和感を覚えたり、痰のからんだような咳が出ることがあります。
【参考情報】『Postnasal Drip』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23082-postnasal-drip
特に、夜間や朝方に咳が強くなることが多く、風邪が治った後も咳だけが長引く場合、副鼻腔炎が原因となっている可能性があります。
<においがわからない(嗅覚障害)>
鼻の粘膜が腫れて空気の通りが悪くなると、嗅覚を司る神経ににおいの成分が届かなくなり、「においがしない」「味がわからない」といった嗅覚障害が現れることがあります。
この症状は急性副鼻腔炎でも起こりますが、慢性化すると長期間にわたりにおいを感じづらくなることがあり、日常生活に支障をきたします。
<子どもや高齢者に特有の症状>
子どもの副鼻腔炎では、発熱、ぐずり、食欲不振などが目立つことがあります。子どもは言葉で症状をうまく伝えられない場合があるため、鼻水の色や様子をよく観察することが大切です。
高齢者の場合は、顔の痛みや鼻水といった典型的な症状が出にくく、代わりに倦怠感や集中力の低下などの全身症状として現れることがあります。体調不良の原因がわかりにくい場合にも、副鼻腔炎が隠れていることがあります。
2.副鼻腔炎の原因とリスク要因
副鼻腔炎は、風邪やアレルギーがきっかけで発症することが多い病気です。
2-1.風邪との関係
副鼻腔炎の最も一般的な原因のひとつが「風邪」です。風邪をひくと鼻の粘膜が腫れ、副鼻腔と鼻をつなぐ通路がふさがれやすくなります。その結果、副鼻腔内に粘液や膿がたまり、細菌やウイルスが繁殖しやすくなるのです。
特に風邪をひいてから数日後に鼻水の色が黄色や緑色に変化し、顔の痛みや頭痛が出てきた場合は、副鼻腔炎に移行している可能性が高いため注意が必要です。
2-2.アレルギー性鼻炎との関連
アレルギー性鼻炎も副鼻腔炎の原因としてよく知られています。アレルギーによって鼻の粘膜が慢性的に腫れると、副鼻腔の通気性や排出機能が低下し、炎症が起こりやすくなります。
特に花粉症やハウスダストアレルギーを持つ人は、副鼻腔炎を繰り返しやすい傾向があります。アレルギー性鼻炎のコントロールが、副鼻腔炎の予防にもつながります。
2-3.細菌・ウイルス感染
細菌やウイルスが副鼻腔内に侵入することで、副鼻腔炎が発症することがあります。ウイルスが原因であれば自然に回復することもありますが、細菌感染を伴うと炎症が強まり、抗菌薬での治療が必要になることがあります。
重症化した場合、発熱や強い顔の痛み、膿のような鼻水などの症状が出ることもあり、早めの対応が大切です。
2-4.生活習慣や環境の影響
喫煙は副鼻腔の粘膜に悪影響を及ぼし、異物を排出する機能を低下させるため、副鼻腔炎のリスクを高めます。副流煙も同様に影響があるため、家庭内の喫煙にも注意が必要です。
また、乾燥した空気は粘膜の防御力を弱めるため、副鼻腔炎のリスクを高めます。
その他、睡眠不足や過度なストレスも免疫のはたらきを低下させる要因となるため、健康的な生活を心がけることが予防につながります。
3.副鼻腔炎の検査と診断方法
この章では、副鼻腔炎が疑われる場合に行う検査を紹介します。
3-1.問診・視診
診察ではまず、医師による問診が行われます。いつから症状が出ているのか、どのような症状があるのか、過去に同様の症状があったかなどを詳しく確認します。
その後、鼻の中を観察する視診が行われ、粘膜の腫れ具合や鼻水の性状をチェックします。
この時点である程度の診断が可能な場合もありますが、より詳細な状況を確認するために、画像検査などが行われることもあります。
3-2.画像検査
副鼻腔内の炎症や膿のたまり具合を視覚的に確認するために、レントゲンやCT検査が用いられます。レントゲンでは副鼻腔の白濁や液体のたまりを確認でき、CTではより詳細な構造や病変の広がりを三次元的に把握できます。
特に慢性副鼻腔炎が疑われる場合や、手術を検討する際にはCT検査が重要な判断材料となります。
3-3.鼻鏡検査
鼻の奥を直接観察する検査です。細いスコープを鼻の中に挿入し、モニターに映し出された映像を見ながら診察が行われます。これにより、粘膜の状態や膿のたまり、ポリープの有無などが確認できます。
4.副鼻腔炎の治療法
副鼻腔炎の治療は薬物療法が中心となりますが、症状が重く長引く場合は手術を行うこともあります。
4-1.薬物療法
副鼻腔炎の多くは薬物療法によって改善が期待できます。急性副鼻腔炎で細菌感染が疑われる場合には、抗菌薬が処方されることがあります。また、鼻づまりの改善には血管収縮作用を持つ点鼻薬、炎症を抑えるためにはステロイド点鼻薬が用いられます。
これらの薬は一時的に症状を和らげるだけでなく、慢性化を防ぐためにも重要です。ただし、点鼻薬の長期使用は逆に粘膜を傷めるリスクもあるため、医師の指導に従って正しく使用することが大切です。
4-2.手術治療
慢性副鼻腔炎や薬物療法で十分な効果が得られない場合、手術治療が検討されます。現在主流となっているのが、「内視鏡下副鼻腔手術(ESS)」です。これは、内視鏡を使って副鼻腔の排出口を広げ、膿や粘液の排出を促す治療法です。
【参考情報】『Endoscopic Sinus Surgery』Johns Hopkins Medicine
https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/endoscopic-sinus-surgery
ESSは体への負担が比較的少なく、入院期間も短いのが特徴です。手術後は、再発予防のために継続的な通院や鼻洗浄などのセルフケアが求められます。
4-3.慢性副鼻腔炎への対応
慢性副鼻腔炎は長期間にわたって炎症が続く状態であるため、治療も長期的な視点で行う必要があります。抗菌薬の長期投与や、ステロイド薬の使用が中心となるほか、アレルギーの有無を確認し、その対策も同時に行われます。
近年では、重症の慢性副鼻腔炎に対して生物学的製剤「デュピクセント」を用いた治療も始まっており、特にポリープを伴うタイプの患者さんには大きな効果が期待されています。
5.自宅でできる副鼻腔炎対策とケア
自分でできる対策としては、鼻うがいや部屋の加湿、生活習慣の見直しなどがあります。
5-1.鼻うがいの方法と注意点
副鼻腔炎のセルフケアとして効果的なのが鼻うがいです。生理食塩水を使って鼻の中を洗浄することで、膿や粘液を排出しやすくし、症状の改善や再発予防につながります。市販の鼻うがいキットもあり、自宅で簡単に実践できます。
ただし、正しい方法で行うことが大切です。冷たい水や水道水をそのまま使うと、粘膜を傷めたり感染のリスクが高まる可能性があるため、ぬるま湯で調整された生理食塩水を使用しましょう。
5-2.加湿と室内環境の整え方
空気の乾燥は鼻や副鼻腔の粘膜にとって大敵です。乾燥すると粘液の流れが悪くなり、炎症が起こりやすくなります。特に冬場やエアコン使用時は、加湿器で室内の湿度を保つことが大切です。
また、ハウスダストや花粉、タバコの煙といった刺激物も副鼻腔炎を悪化させる原因となるため、空気清浄機の活用やこまめな換気・掃除など、室内環境を清潔に保つよう心がけましょう。
5-3.食事・睡眠・ストレス管理
免疫のはたらきを高めることは、副鼻腔炎の予防と回復において非常に重要です。栄養バランスのとれた食事、特にビタミンCや亜鉛、タンパク質などを意識的に摂るようにしましょう。
◆「ビタミンCのおもな特徴とアレルギー疾患を改善するはたらき」>>
さらに、質の良い睡眠をとることや、ストレスをため込まない生活習慣も粘膜の健康を維持するために欠かせません。規則正しい生活を送ることが、副鼻腔炎を遠ざけるための基本となります。
6.副鼻腔炎を予防するには?
副鼻腔炎を予防するには、風邪やアレルギー、ストレスなどへの対策がおすすめです。
6-1.呼吸器感染症の予防
副鼻腔炎の多くは、風邪などの呼吸器感染症をきっかけに発症します。そのため、風邪をひかないよう日常的に予防することが大切です。
外出後の手洗いやうがい、人混みでのマスク着用、十分な睡眠と栄養の摂取など、基本的な感染予防策を徹底しましょう。
6-2.アレルギー対策
アレルギー性鼻炎は副鼻腔炎を誘発する原因の一つです。アレルギー反応によって鼻の粘膜が腫れると、副鼻腔の通気や排泄が妨げられ、炎症が起こりやすくなります。
花粉症の季節には外出時のマスクやメガネ、帰宅後の衣類の着替え・シャワーなどでアレルゲンの付着を防ぎましょう。
室内では空気清浄機を使用したり、こまめな掃除でホコリやダニを減らすことも有効です。
6-3.生活習慣の見直し
不規則な生活やストレス、喫煙といった生活習慣は、粘膜の状態を悪化させ、副鼻腔炎のリスクを高めます。毎日の睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを整えることが重要です。
また、喫煙は副鼻腔の粘膜を刺激し、炎症を助長するため、副鼻腔炎の予防のためには禁煙が推奨されます。小さな積み重ねが、大きな予防効果につながります。
7.副鼻腔炎と間違いやすい病気
鼻や喉に炎症が起こる病気にかかると、副鼻腔炎に似た症状が出ることがあります。
7-1.アレルギー性鼻炎
副鼻腔炎とよく混同される病気のひとつがアレルギー性鼻炎です。どちらも鼻水や鼻づまりが主な症状ですが、アレルギー性鼻炎ではくしゃみや目のかゆみ、透明でサラサラした鼻水が特徴です。
【参考情報】『アレルギー性鼻炎/Q&A』日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=5
一方、副鼻腔炎では粘り気のある黄色〜緑色の鼻水、顔の痛み、嗅覚障害などがみられ、風邪の延長で発症することが多いのが違いです。症状が似ているため、医療機関での正確な診断が大切です。
7-2.鼻ポリープ
鼻ポリープ(鼻茸)は、副鼻腔や鼻腔内にできる良性の腫瘍で、慢性的な炎症によって生じます。鼻づまりが強くなり、においがわからなくなるなど、副鼻腔炎に似た症状を呈します。
鼻ポリープは慢性副鼻腔炎に合併することも多く、内視鏡検査で発見されます。大きなポリープや症状の強い場合は手術で除去されることがあります。
7-3.上咽頭炎
上咽頭炎は、鼻の奥から喉にかけての部位である「上咽頭」に炎症が起きる疾患です。後鼻漏や喉の違和感、慢性的な咳が主な症状で、副鼻腔炎と症状が重なる部分もあります。
慢性化すると集中力の低下や不眠、耳の違和感などを訴える人もおり、EAT(上咽頭擦過療法)という治療法が行われることがあります。
8.副鼻腔炎に関するよくある質問と答え
この章では、副鼻腔炎に関するよくある質問を紹介します。
8-1.副鼻腔炎は自然に治る?
急性副鼻腔炎の中には、軽症であれば自然に治るケースもあります。しかし、症状が長引いたり、膿のような鼻水や強い頭痛、発熱などが見られる場合には細菌感染が疑われ、抗菌薬などでの治療が必要です。
特に慢性副鼻腔炎では自然治癒が難しく、長期的な治療や生活習慣の見直しが求められることもあります。
8-2.副鼻腔炎は市販薬で治せる?
市販の点鼻薬や風邪薬で一時的に症状が和らぐことはありますが、根本的な治療にはなりません。
また、点鼻薬の使いすぎはかえって症状を悪化させることもあるため、用法・用量を守ることが大切です。
8-3.耳や目への影響は?
副鼻腔は耳や目と近接しているため、重症化すると中耳炎や視力への影響が出ることもあります。
特に目の周囲の腫れや視力の低下がみられる場合は、緊急性を要する可能性があるため、すぐに医療機関を受診しましょう。
9.おわりに
副鼻腔炎は再発しやすい疾患でもありますが、日頃の生活習慣を見直すことで予防が可能です。風邪予防や室内環境の整備などを継続することで、症状の発生を抑えることができます。
また、副鼻腔炎は、アレルギーと密接な関係のある病気でもあります。思い当たる方はアレルギーの原因となるハウスダストや花粉などの物質を避けるため、こまめな掃除や空気清浄機の使用、外出時のマスク着用などを実施しましょう。