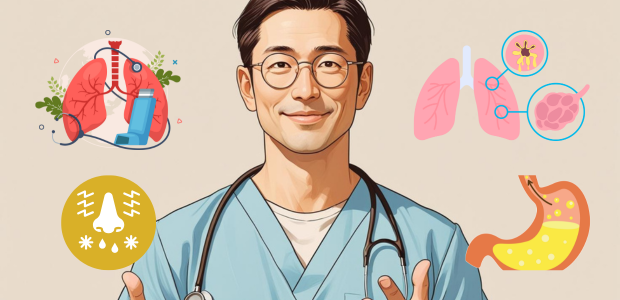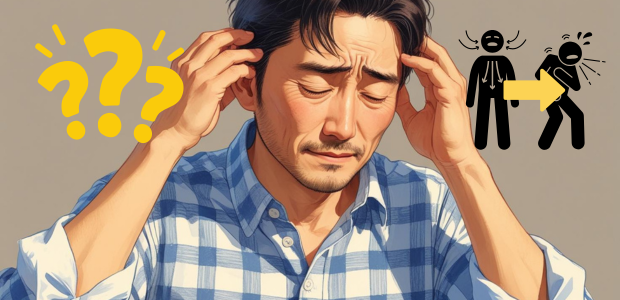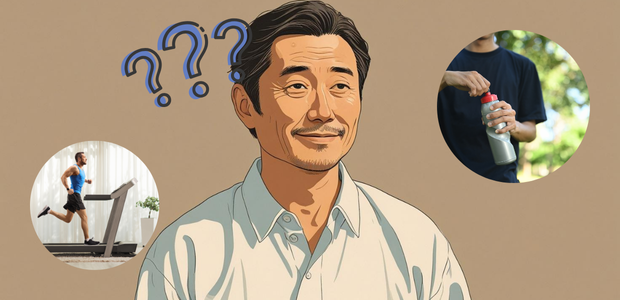息を吸うと咳が出る――風邪?それとも別の病気?

「深く息を吸った瞬間に咳が出る」「冷たい外気を吸ったらむせてしまう」という経験は珍しくないでしょう。
こういう場合、「ただの風邪かな?」と思って放置しがちですが、繰り返し起こるようなら、風邪以外の原因が潜んでいるかもしれません。
この記事では、息を吸うと咳が出る原因と考えられる病気を紹介します。自分でできる対策や受診の目安も紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
1.なぜ咳が出るのか
咳は、ウイルスのような異物から体を守るために必要な、重要な反応です。
1-1.咳が出る仕組みと咳が誘発される理由
のどや気管の粘膜には細かいセンサーのような神経があり、刺激を感知すると咳反射が起こり、不要な異物を外へ押し出そうとします。
ところが風邪やアレルギーで炎症が残っていると、このセンサーが過敏になってしまい、ほんの少しの刺激にも反応しやすくなり、咳が誘発されます。
すると、冷たい外気を吸い込んだり、深呼吸をしたときに咳き込みやすくなります。
【参考情報】『Cough』Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/17755-cough
1-2.咳が続く期間が長ければ病気の可能性が
咳には続く期間による分類があります。
・急性咳嗽(きゅうせいがいそう):3週間未満
・遷延性咳嗽(せんえいせいがいそう):3〜8週間
・慢性咳嗽(まんせいがいそう):8週間以上
このうち、特に慢性咳嗽の場合は、単なる風邪ではなく別の病気が関わっている可能性が高くなります。
「息を吸うと咳が出る」という症状は、単なる風邪よりも、こうした慢性疾患で繰り返し見られることが多いのです。
2.息を吸うと咳が出るときに考えられる主な病気
咳の原因の多くは呼吸器疾患ですが、消化器の病気など別の原因によるものもあります。
2-1.喘息
喘息は、空気の通り道である気道に慢性的な炎症が起きて狭くなり、敏感になる病気です。
主な症状は咳、息苦しさ、喘鳴(ぜんめい:息を吐くときにゼーゼー・ヒューヒューと音がする)で、冷たい空気や運動、深呼吸といったちょっとした刺激で咳が出やすくなります。
2-2.咳喘息
咳喘息は、典型的な喘息のような「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音や強い息苦しさはなく、乾いた咳だけが長く続く病気です。
風邪やコロナが治ったあとに、咳だけが何週間も残る場合に疑われます。
咳喘息も喘息と同じように、冷たい外気を吸ったときや深呼吸が刺激となって咳が出ることがあります。
咳喘息を放置すると、本格的な喘息に移行することがあるため、早期に診断して治療を始めることが大切です。
2-3.COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPDは、長年の喫煙などによって気道や肺に炎症が起こり、呼吸のしにくくなる病気です。
主な症状は、慢性的に続く咳や痰、息切れで、進行すると少しの動作でも息苦しさを感じます。
COPDの患者さんは気道に痰が残りやすく、息を吸ったときにその痰が気道を刺激して咳が出ることがあります。
特に朝方に咳や痰が増える人は多く、深く息を吸ったときや冷たい空気を吸い込んだときに咳が出やすいのも特徴です。
中高年の喫煙者に多く見られる病気のため、咳が出ても「年齢のせい」だと思いがちですが、放置すると肺機能が徐々に低下するため、早期発見と禁煙、治療が重要です。
◆「咳がとまらない・しつこい痰・息切れは、COPDの危険信号」>>
2-4.後鼻漏(こうびろう)
後鼻漏とは、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などによって出た鼻水が、のどの奥に流れ込んでしまう状態を指します。
◆「副鼻腔炎とはどんな病気?咳・アレルギー・いびきとの関係」>>
「のどに何かがへばりついている」「いつも痰がある」と感じることが多いです。
後鼻漏では、鼻水が気道に流れ込み、息を吸ったときに一緒に吸い込まれることで咳が出ます。
特に寝ている間や横になったときに咳が増えるのが特徴で、朝起きたときに咳や痰が多い場合は後鼻漏が疑われます。
2-5.胃食道逆流症(GERD)
胃食道逆流症は、胃の内容物や胃酸が食道を逆流してのどに達し、気道を刺激する病気です。胸やけやゲップを伴うことが多く、横になると症状が悪化しやすいのが特徴です。
逆流した胃酸がのどに残っている状態で息を吸うと、それを気道に吸い込んでしまい、咳が出ることがあります。
夜寝ているときや朝方に咳が強くなる人は、胃食道逆流症の影響を受けている可能性があります。
2-6.間質性肺炎
間質性肺炎は、肺の奥にある「間質」と呼ばれる組織に炎症や線維化(硬くなる変化)が起こり、酸素を取り込みにくくなる病気です。
進行すると息切れが強くなり、痰を伴わない乾いた咳が長く続きます。特に深く息を吸ったときに咳が出やすくなります。
2-7.薬の副作用
高血圧の治療薬であるACE阻害薬には、副作用として乾いた咳を起こすものがあります。
【参考情報】『ACE阻害薬』日本心臓財団
https://www.jhf.or.jp/check/term/word_a/ace/
薬を飲み始めてから「息を吸うと咳が出やすい」と感じる場合は、この副作用の可能性がありますが、自己判断で薬を中止するのは危険ですので、必ず主治医に相談しましょう。
3.風邪との違い
咳は風邪でもよく出る症状ですが、「息を吸うと咳が出る」という特徴は必ずしも風邪に当てはまりません。
風邪の場合、咳は発熱や鼻水、のどの痛みとセットで現れることが多く、1〜2週間以内に自然に改善するのが一般的です。
一方で、喘息や咳喘息では、冷たい空気や深呼吸など、吸った息そのものが咳の誘因になります。
胃食道逆流症の場合は食後や就寝時、横になった際に咳が強まります。
後鼻漏は横になると鼻水がのどに流れ込み、吸気と一緒に気道へ入り込み咳を誘発します。
COPDでは痰が気道に残り、息を吸ったときに痰が動いて咳が起こりやすいのです。
このように「咳が息を吸う動作とリンクしているかどうか」が、風邪かそれ以外かを見分ける重要なヒントになります。
4.受診の目安
息を吸うと咳が出る症状で受診を検討すべき目安は以下の通りです。
・症状が長引いている
症状が2週間以上続く
・咳以外の症状を伴う
息切れ、胸の痛み、体重減少、血痰などがある
・夜間から早朝にかけて咳が増える
睡眠中に咳が出たり、咳がひどくて眠れない
・既往歴やリスクがある場合
喘息やCOPD、間質性肺炎など呼吸器疾患の既往がある場合や、高齢者
・市販薬で改善しない
咳止め薬や生活改善で症状が改善しない
これらに該当する場合は、呼吸器内科など専門医を早めに受診することが重要です。
5.呼吸器内科で行われる検査
呼吸器内科では、問診と聴診だけでなく、さまざまな検査を組み合わせて原因を特定します。
・スパイロメトリー
息を大きく吸って一気に吐き出す検査で、気道の狭さや肺の働きを調べます。咳喘息やCOPDの診断に有用です。
・呼気NO検査
吐いた息に含まれる一酸化窒素を測定する検査で、気道に炎症があるかどうかを判断します。喘息の補助診断に使われます。
・モストグラフ
呼吸のしやすさを調べる検査です。特に喘息やアレルギー性疾患によって気道が狭くなっていないかを評価します。
・胸部レントゲンやCT
肺の構造を映し出し、肺炎や腫瘍、気管支の異常などを調べます。長引く咳や血痰がある場合は特に重要です。
・アレルギー検査
血液検査で特定のアレルゲンに反応していないかを確認し、アレルギー性咳嗽や喘息の背景を探ります。
これらの検査はいずれも比較的負担が少なく、短時間で受けられるものです。結果を総合的に評価することで「息を吸うと咳が出る」原因が明らかになります。
6.息を吸うと咳が出るときにできる生活の工夫
咳を軽くするには、日常生活の中でも刺激を減らす工夫が欠かせません。
・乾燥対策
冬の乾燥した空気は、のどや気道を刺激して息を吸ったときに咳が出やすくなります。
室内の湿度は40〜60%に保つのが理想で、加湿器があれば便利です。加湿器がなくても、濡れタオルを室内にかけるだけでも効果があります。
また、こまめに水分をとることでのどを潤し、咳を和らげることができます。
・冷たい外気の対策
冬の朝、外に出て冷たい空気を吸い込むと、思わず咳き込んでしまうことがあります。
そんな時は、マスクをつけるのがおすすめです。マスクが冷たい空気を温め、湿らせてくれるので、喉や気管への刺激が和らぎ、咳込みにくくなります。
寒い時期に運動をする際も、マスクやスカーフを着用すると、喉への負担を減らすことができます。
・就寝時の工夫
横になると、胃酸の逆流や、鼻水が喉に流れ込む後鼻漏によって咳が出やすくなることがあります。
このような場合は、枕を少し高くして上半身を起こし気味にすると、気道への刺激を減らすことができます。
・禁煙
たばこは咳を悪化させる最大の原因の一つです。たばこの煙が強い刺激となり、咳をさらに悪化させてしまいます。
最も効果的な改善策は禁煙です。また、自分だけでなく、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙も避けるようにしましょう。
・空気をキレイに保つ
掃除や換気をこまめに行い、吸うと刺激となるホコリや花粉などを減らしましょう。空気清浄機を活用するのもいいでしょう。
7.よくある質問(FAQ)
Q1. 息を吸うと咳が出るとき、運動は避けたほうがいいですか?
A1. 寒冷時や空気が乾燥しているときは、マスクやスカーフで空気を温め、室内での軽い有酸素運動から始めると安全です。
咳が強く出る場合は、無理せず休息を優先しましょう。
Q2. 咳が出やすいときに飲み物は何を選べばいいですか?
A2. 常温の水や白湯、カフェインやアルコールを含まないハーブティーがおすすめです。
逆に、冷たい飲み物や酸味の強い飲料は刺激となることがあるので控えましょう。
Q3. 息を吸うと咳が出るのはストレスが原因のこともありますか?
強い緊張やストレスで自律神経が乱れると、気道が過敏になり咳が出ることがあります。
ただしストレスや心の問題と決めつける前に、呼吸器の病気である可能性を除外せずに、検査を受けることが大切です。
Q4. 子どもの場合も息を吸うと咳が出やすいですか?
子どもは気道が細くて刺激に敏感なので、冷たい空気やホコリっぽい空気を吸うと咳が出やすくなります。長引く場合は相談してください。
Q5. 市販の咳止めで治まるなら、病院を受診しなくてもいいですか?
市販薬で一時的に咳が楽になることはありますが、咳の原因そのものがなくなったとは限りません。咳が2週間以上続く場合は必ず医師に相談しましょう。
8.おわりに
息を吸うと咳が出る症状は、風邪で起こることもありますが、長引く場合は喘息やCOPDなどの病気や、薬の影響なども考えられます。
咳は体からの大切なサインです。よくある症状だからと軽視せず、長引く場合や日常生活に支障が出ている場合は、早めに専門医に相談して穏やかな日常を取り戻しましょう。