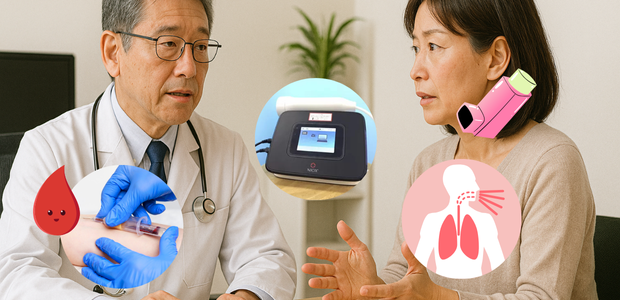重症喘息と生物学的製剤 ― 安心して治療するために知っておきたいこと
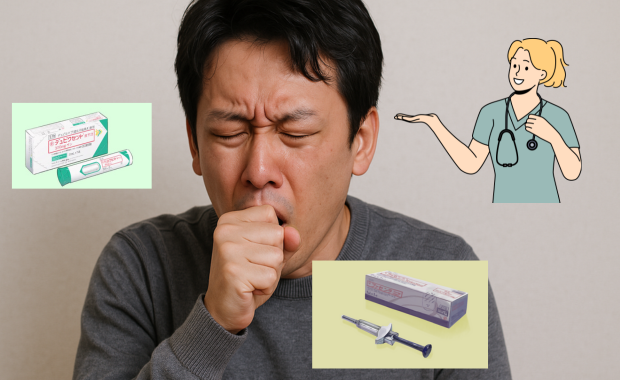
喘息は「息が苦しい病気」と一言で言い表せない、さまざまな症状を持つ慢性の病気です。軽い運動で息切れする人もいれば、夜に何度も目が覚めたり、日中も発作が起こるのではと不安を感じ続ける人もいます。
通常は吸入ステロイド薬(ICS)や長時間作用型β2刺激薬(LABA)を使って症状を抑えますが、これらを正しく使っても症状が改善しない重症の喘息もあります。そうした方のために、新しい治療法として「生物学的製剤」が登場しています。
この記事では、生物学的製剤がどんな薬か、その働き方や生活への影響、治療の始め方、費用や利用できる制度についてわかりやすく解説します。
目次
1.喘息と重症喘息の基礎知識
喘息は、気道の慢性的な炎症によって咳やゼーゼー、胸の締めつけ感、息苦しさが起こる病気です。
炎症の原因は人によってさまざまで、ダニやホコリ、花粉などのアレルギー物質のほか、ウイルス感染、運動、気温の変化、ストレス、空気の汚れなどが関わっています。
世界全体では、2019年時点で約2億6,200万人が喘息を抱えており、毎年約45万5,000人が喘息に関連して亡くなっていると報告されています。
【参考情報】『Asthma』WHO
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
多くの人は吸入薬を正しく使うことで症状を抑え、普段通りの生活を送れますが、最適な治療をしても発作を繰り返す方もいます。
国際的な喘息治療の指針「GINA 2024」では、高用量の吸入ステロイド薬と長時間作用型β2刺激薬を使っても症状が改善しない、かつ年に何回か発作や入院を経験する人を「重症喘息」と定義し、専門的な診断と治療を推奨しています。
【参考情報】『Summary Guide for Asthma Management and Prevention』GINA
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/12/GINA-Summary-Guide-2024-WEB-WMS.pdf
重症喘息になると、夜や早朝に息苦しくて眠れなくなったり、天気や季節の変化で症状が悪化しやすくなります。また、階段の昇り降りが辛くなったり、外出や運動を控えるようになり、日常生活の質が大きく下がります。
2.生物学的製剤とは?
生物学的製剤は、体内の炎症を引き起こす特定の物質を狙って働く最新の治療薬です。
2-1.定義と作用の考え方
生物学的製剤は、細胞や遺伝子を使って作られる特別な薬で、モノクローナル抗体という種類の薬がよく知られています。
この薬は、体の中で炎症を引き起こす特定の物質(サイトカインや受容体)にピンポイントでくっつき、その働きを止めることで炎症を抑えます。
アメリカの食品医薬品局(FDA)の生物製剤評価センター(CBER)は、生物学的製剤を「タンパク質を主成分とする治療薬など、生物由来の多様な製品」と定義し、厳しい安全性と効果の審査を経て承認しています。
【参考情報】『Resources for You (Biologics)』FDA
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/resources-you-biologics
2-2.生物学的製剤の種類
現在、喘息治療で使われている主な生物学的製剤は以下の通りです。
<ヌーカラ(メポリズマブ)>
好酸球性喘息に用いられ、IL-5という炎症を促進するタンパク質に結合して働きを抑えます。
国際共同試験(MENSA試験)では、重症好酸球性喘息患者で年間の発作回数を約47〜53%減少させました。また、ステロイド内服量の削減効果も認められました。
【参考情報】『Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma』The New England Journal of Medicine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1403290
◆「ヌーカラ」についてくわしく>>
<デュピクセント(デュピルマブ)>
IL-4およびIL-13という二つの炎症経路を同時に抑えるため、多様な重症喘息に対応可能です。喘息だけでなくアトピー性皮膚炎などの治療にも使われます。
臨床試験では、中等症〜重症喘息患者で発作回数が有意に減少し、投与2週目から肺機能(FEV₁)が改善、その効果は1年以上持続しました。特に好酸球値が高い患者で効果が顕著でした。
【参考情報】『Dupilumab Efficacy and Safety in Moderate-to-Severe Uncontrolled Asthma』The New England Journal of Medicine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804092
◆「デュピクセント」についてくわしく>>
<テゼスパイア(テゼペルマブ)>
喘息のタイプを問わず使用できる比較的新しい薬で、炎症の初期に関与するTSLPに作用し、さまざまな炎症反応を抑制します。
臨床試験では、好酸球数やアレルギーの有無を問わず、幅広い重症喘息患者で年間発作回数を56%減少させました。炎症マーカー(FeNO・好酸球数)も改善しました。
【参考情報】『Tezepelumab in Adults and Adolescents with Severe, Uncontrolled Asthma』The New England Journal of Medicine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034975
◆「テゼスパイア」についてくわしく>>
<ファセンラ(ベンラリズマブ)>
IL-5受容体に結合し、好酸球を直接減少させることで強力な炎症抑制効果を持ちます。投与間隔が長いのも特徴です。
臨床試験では、重症好酸球性喘息患者に対してベンラリズマブ投与により、年間発作率が最大51%減少し、FEV₁(肺機能)も改善したことが報告されています。
【参考情報】『Treating eosinophilic exacerbations of asthma and COPD with benralizumab (ABRA): a double-blind, double-dummy, active placebo-controlled randomised trial』The Lancet
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(24)00299-6/fulltext
◆「ファセンラ」についてくわしく>>
<ゾレア(オマリズマブ)>
IgE抗体に結合し、アレルギー反応を引き起こすIgEの働きを抑えます。アレルギー性喘息に特に効果的です。
臨床試験では、ゾレアは重症アレルギー性喘息患者で、プラセボに比べて増悪率を26%減少させ、症状やQOLも改善しました。
【参考情報】『ゾレア 製品について 有効性と安全性(成人)』ノバルティス ファーマ
https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/clinical_03
◆「ゾレア」についてくわしく>>
これらの薬剤は、炎症の仕組みや患者さんの症状に合わせて使い分けられます。
2-3.従来の治療との違い
これまでの吸入ステロイド薬(ICS)は、気道全体の炎症を広く抑える薬ですが、喘息の原因となる炎症の種類は人それぞれ異なります。
例えば、IgEやIL-5といった特定の炎症物質が主に働いている場合、従来の薬だけでは十分に効果が出ないことがあります。
生物学的製剤は、そうした「炎症の主要な原因」を分子レベルで狙い撃ちするため、重症の喘息患者さんで発作を減らしたり、ステロイドの量を減らす効果が期待できます。
3.治療の流れ
重症喘息の治療に生物学的製剤を導入する際は、まず過去の治療内容や症状、環境要因を丁寧に確認し、必要な検査で炎症タイプを把握します。
その上で、薬の適応条件や特徴、安全性などを主治医と相談し、同意を得て導入を進めます。
3-1.症状と治療歴の確認
まずは、これまで使ってきた治療薬の種類や量、吸入のやり方、きちんと続けられているか(アドヒアランス)を詳しく確認します。
【参考情報】『アドヒアランス』日本ジェネリック製薬協会
https://www.jga.gr.jp/jgapedia/column/201702.html
また、発作(増悪)がどのくらいの頻度で起きているか、夜間に息苦しさがあるか、救急や入院の経験も整理します。
吸入薬の使い方の誤りや、ダニや喫煙、職場での有害物質など環境の問題を改善するだけで症状がよくなる場合もあるため、まずは現在の治療をできる限り最適にすることが優先されます。
3-2.検査で炎症のタイプを調べる
重症喘息の多くは「Th2(タイプ2)炎症」という特定の炎症が関わっています。
【参考情報】『タイプ 2 炎症バイオマーカーの手引き』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/publication/file/type2_IB.pdf
血液検査では、好酸球という白血球の数が150〜300/μL以上だったり、呼気中の一酸化窒素(FeNO)が25ppb以上だったり、IgEというアレルギーの指標が高いか、アレルギー検査で特定の物質に反応がある場合があります。
これらの検査結果は治療の選択に役立ちます。特にFeNOは、米国胸部疾患学会(ATS)のガイドラインでも、25ppb以上は好酸球性炎症を示す目安とされています。
【参考情報】『An Official ATS Clinical Practice Guideline: Interpretation of Exhaled Nitric Oxide Levels (FeNO) for Clinical Applications』American Thoracic Society
https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.9120-11ST
3-3.治療方針の相談
これらの検査結果や症状の評価をもとに、生物学的製剤が使えるかどうかを主治医と話し合います。
生物学的製剤は、「高用量の吸入ステロイド薬と長時間作用型β2刺激薬を使っても症状が安定しない」「年に何回か発作や入院がある」といった条件を満たす患者さんが対象です。
薬ごとに使用できる年齢や投与の間隔、自己注射の可否、安全性、費用、通院のしやすさなど特徴が異なるため、これらを詳しく説明してもらい納得してから治療を始めます。
3-4.同意と導入
初めての投与は、アレルギー反応などの安全確認のため病院で行うのが一般的です。
その後は、薬剤の種類や患者さんの状況に応じて、通院しながら注射する方法か、自宅で自己注射を選択できます。
3-5.効果の確認
生物学的製剤を使い始めたら、3〜6か月ごとに効果をしっかりチェックします。たとえば、
・発作がどれくらい減ったか
・救急外来や入院が必要になることがあったか
・普段使っている吸入薬の使用状況
・好酸球の数や、呼気(息)に含まれる炎症のサイン(FeNO)
・肺の働き(どれだけ息を吸ったり吐いたりできるか)
といった項目を総合的に見ます。
もし十分な効果が得られない場合は、薬を正しく使えているかや生活環境の影響を確認し、それでも改善が見られなければ、別の種類の生物学的製剤への切り替えを検討します。
4.通院や自己注射の選択
生物学的製剤は、薬の種類によって「病院で医療スタッフが行う皮下注射や点滴」と、「自宅で自分で注射する自己注射(薬液が充填された注射器であるオートインジェクターなどを使う)」のどちらかを選べる場合があります。
<病院での投与>
医療スタッフが注射や点滴の手技を行い、もしアレルギー反応などの急なトラブルがあってもすぐに対応できる安心感があります。
<自己注射>
通院回数を減らせるため、仕事や子育てなど忙しい日常と両立しやすくなります。使用前には注射の方法や薬の保管、使用済み針の処理方法などについて指導を受け、急な体調変化があった場合の連絡体制も確認しておくことが重要です。
初めて使うときは、安全面から病院での投与と経過観察が推奨されています。その後は、患者さんの生活スタイルや希望、また薬の承認条件に応じて自己注射に切り替えることが可能です。
通常、注射の頻度は2週間から8週間に1回程度で、通院が難しい方でも続けやすい仕組みになっています(対応可否は薬剤によって異なります)。
5.費用と制度
生物学的製剤は薬価が高額なため、費用負担を心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、日本ではこれらの薬は公的医療保険の対象で、自己負担は年齢や所得に応じて1〜3割に抑えられます。
さらに、高額療養費制度を利用すれば、毎月の自己負担額には上限が設けられており、上限を超えた分は払い戻されます。例えば、年収約370〜770万円の方では上限が月約8〜9万円程度となります。
高額療養費制度は事後申請も可能ですが、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払い時から上限額が適用されるため負担を軽減できます。自己注射で自宅使用する場合も保険適用の対象です。
マイナ保険証で受診する場合は、限度額適用認定証の手続きは不要です。
【参考情報】『高額な外来診療を受ける皆さまへ』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html
6.生活環境の整え方と日常の工夫
<ダニやほこりの除去>
寝具カバーは防ダニ効果のある素材を選び、週に1回以上は洗濯(60℃以上が目安)し、掃除機もこまめにかけましょう。カーペットやぬいぐるみはできるだけ減らし、布団は天日干しや乾燥機で湿気をためないようにすることが大切です。
<換気と湿度の管理>
室内の湿度は40〜60%に保つのが理想的です。季節に応じて加湿器や除湿器を使い分け、入浴や料理の際には換気扇を使って空気を入れ替えましょう。
<空気清浄機の活用>
HEPAフィルター搭載の空気清浄機は、花粉や微細な粒子を減らすのに効果的です。玄関では衣類のほこりをはたき、上着は一時的に別の場所に置くなどの工夫も役立ちます。
<ペットの管理>
ペットは寝室に入れないようにし、こまめなブラッシングや部屋の掃除を行いましょう。
<喫煙と受動喫煙の回避>
家の中は完全禁煙にしましょう。加熱式たばこでも微細な粒子が発生するため、注意が必要です。
<無理のない運動>
症状が安定している時に、準備運動(ウォーミングアップ)、本運動、終わりの運動(クールダウン)の順で行いましょう。寒い日は屋内で軽めの運動に切り替えると安全です。
<ストレス管理と睡眠の質向上>
毎日同じ時間に寝起きし、昼夜逆転を避けます。寝室の光や音、温度環境を整え、寝る前のスマホ使用は控えましょう。
<感染予防>
手洗い・うがい・マスクの着用を習慣にし、体調が悪い時は早めに医療機関を受診し、十分に休養をとりましょう。
7.よくある質問
Q1. 生物学的製剤は発作が起きたときにすぐ効く薬ですか?
A1. いいえ。生物学的製剤は発作をその場で止める薬ではなく、炎症や免疫反応を長期的に抑えて発作を起こりにくくする薬です。発作時には、これまで通り速効性の吸入薬(リリーバー)を使います。
◆「リリーバー(発作治療薬)・メプチンの特徴と効果、副作用」>>
Q2. 生物学的製剤を使い始めると、今までの吸入薬はやめられますか?
A2. 多くの場合、最初はこれまでの吸入薬と併用します。症状が安定すれば、医師が吸入薬の量を減らすことを検討する場合もありますが、急に中止すると症状が悪化することがあります。
Q3. 生物学的製剤にはどんな副作用がありますか?
A3. 注射部位の赤みや腫れ、軽い発疹などが起こることがあります。まれにアナフィラキシーなどの重いアレルギー反応が出ることがあるため、初回は医療機関での投与が推奨されます。
Q4. 自己注射が不安な場合はどうすればいいですか?
A4. 医師や看護師から注射の手順や注意点を練習してから自宅で行います。不安がある場合や体調が悪いときは、無理せず医療機関で注射してもらうこともできます。
Q5. 生物学的製剤は一生使い続ける必要がありますか?
A5. ずっと使う必要があるとは限りません。症状が安定し、発作がほとんど起きなくなった場合には、医師と相談のうえで減量や中止を検討することもあります。
8.おわりに~安心して選択するために
生物学的製剤は、これまでの吸入薬をしっかり使っても症状が良くならない重い喘息に対して、発作を減らしたり症状を和らげたりする新しい治療法です。
ただし、誰にでも使えるわけではありません。治療の対象となる条件に当てはまるか、今の薬の使い方が最適かどうか、副作用や費用のこと、通院や自宅での自己注射ができるかなど、いろいろな点を考えて主治医と一緒に納得できる選択をすることが大切です。
また、この治療を続けるかどうかは、最新の医学的な情報やガイドラインに基づき、効果や安全性、費用とのバランスを定期的に見直すことが重要です。